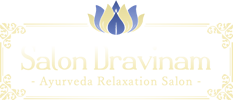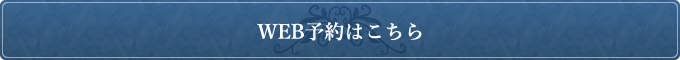- ホーム
- "a more fulfilling life" ブログ
"a more fulfilling life" ブログ
腸内細菌が支える
腸の働き その5
2021/02/26
腸の働きには大きく7つあります。
その7つの働きとは、「合成」、「消化」、「吸収」、「排泄」、「解毒」、「浄血」、「免疫」です。
それを1つ1つ探っていきます。
今回は腸の働きの解毒についてお話ししていきます。
腸の働き 「解毒」
解毒(デトックス)と聞くと、ちょっと耳を傾けてしまうのが女性という生き物(笑)
デトックスとは、体内に入ってきたもの、蓄積された老廃物や有害物質を体の外に出すことです。
この機能はもともと人の体に備わっています。
それが肝臓です。
お酒などのアルコールや防腐剤などの食品添加物をはじめとして、薬剤なども体にとっては有害物質です。
肝臓はこうした有害物質を分解、処理して、体の外に排出します。
食べた物が消化吸収される際に体内で発生するアンモニアも肝臓で尿素に変換し体外に排出してくれます。
腸の働きの話じゃないのって思われました?
ここから腸の登場です。
この肝臓の働きをサポートしてくれているのが腸です。
体外からの有害物質が最初に接触する場所が実は腸なのです。
腸は体外から入ってくる有害物質をブロックするバリア器官です。
腸がブロックできなかった有害物質が肝臓に運ばれて解毒処理されます。
つまり、腸がきちんと機能してくれていないと、肝臓には大量の有害物質が流れ込んでしまいます。
腸内には200種100兆個以上もの腸内細菌がすんでいます。
中には食べた物を分解する過程で有害な物質を産生してしまう細菌もいます。
そして、その産生してしまった有害な物質を代謝してくる細菌もいます。
有害な物質を産生してしまう細菌だけが増えてしまい、有害な物質を代謝してくれる細菌が減ってしまうと、有害物質が増えて肝臓の負担が増してしまいます。
大事なのはそのバランスです。
腸内細菌のバランスを保つことが最大のデトックス効果を発揮してくれます。
腸でつくられるガスがおならとして体外に出てきます。
腸内細菌が食べ物を分解する時に出すガスの多くは、水素やメタンでほとんど匂いがありません。
腸内細菌のバランスが乱れてアンモニアや硫化水素などのガスが偏って出ると、かなり臭いおならになります。
前回もお話ししましたが、おならの臭いは腸内細菌のバランスを映し出してくれます。
いつもより臭いなーと感じたら食生活を見直しましょうね。
腸内細菌が支える
腸の働き その4
2021/02/22
腸の働きには大きく7つあります。
その7つの働きとは、「合成」、「消化」、「吸収」、「排泄」、「解毒」、「浄血」、「免疫」です。
それを1つ1つ探っていきます。
今回は腸の働きの排泄についてお話ししていきます。
腸の働き 「排泄」
便の内容物は70〜80%が水分。
残りの30〜20%が食べかす、腸内細菌、腸粘膜などです。
便の形成と排泄を大腸内で行っています。
小腸までに消化吸収された食べ物は、水分が多くてドロドロしています。
大腸内を移動している間に、水分吸収されて固形化されます。
この移動の鍵となるのが、『ぜんどう運動』と『粘液の分泌』です。
ぜんどう運動により、便を肛門まで運びます。
この時、便が大腸の細胞を傷つけないようにするために、大腸から粘液が出て、便を滑りやすくします。
肛門近くまで運ばれてくると、最後に大腸が水分を出して、便は肛門から排泄されます。
便には体内の不要物や有害物質が含まれています。
痛風の原因となる尿酸も、便から排泄されていることが分かってきたそうです。
便の排泄は、体内の不要物を排泄するためになくてはならないものなのです。
便秘は、この不要物を体内に止まらせてしまう恐ろしい症状です。
便秘知らずの健康な大腸でいるためには、『ぜんどう運動』と『粘液の分泌』が正常に機能されることが大切です。
そして、その二つをコントロールしているのが『短鎖脂肪酸』です。
短鎖脂肪酸は、ぜんどう運動、粘液の分泌、腸壁細胞の保護などに必要なものです。
短鎖脂肪酸は食べ物にも含まれています。
でも、おおかた小腸で吸収、代謝されてしまいます。
大腸にとっても必要なものなのに!
では、大腸に必須の短鎖脂肪酸をどうやって確保しているのでしょうか?
それは、腸内細菌が作ってくれています。
食べたものからでは大腸に必要な短鎖脂肪酸が届かないから、腸内細菌が働いてくれているのです。
腸内細菌が作ってくれるから小腸ですべて吸収、代謝してしまうのですね。
腸内に住んでいる200種、100兆個もの腸内細菌の中の一部が、消化吸収されない食物繊維を原料にして、短鎖脂肪酸を作り出しています。
短鎖脂肪酸にはさまざまな種類があり、その役目も違います。
この、短鎖脂肪酸を多くスムーズに産生することが、スムーズな排便につながります。
偏った食事はこの産生の妨げになります。
食事のバランスが悪いと腸内細菌のバランスも乱れてしまう原因になるからです。
腸内細菌のバランスの乱れは短鎖脂肪酸の乱れに直結してしまいます。
だから、野菜、肉、魚、海藻類、きのこ類、など、まんべんなく食べることが大切です。
多くの食物繊維を摂取することもポイントになります。
「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」をバランスよく摂るようにしましょう。
水溶性食物繊維は、りんご、海藻、こんにゃくなどです。
不要性食物繊維は、さつまいも、ごぼうなどです。
ちなみに、私はこの二つをバランスよく摂る工夫として、ゴボウとこんにゃくを一緒に、みりん、しょうゆで炒め煮にして常備野菜にしてます。
さつまいもと海藻類は味噌汁の具に頻繁に登場します。
腸内環境が悪いのかどうかよくわからないと言う人は、ご自身のおならや便の臭いで判断できますよ。
鼻をつまみたくなるような臭さだと、腸内環境は良くありません。
臭いが臭くなってきたら便秘の前兆と思って、食生活の見直しをしてみてください。
まとめ
- 便を排泄させるためには、ぜんどう運動と粘液の分泌が重要
- 体外に不要物を排泄してくれるのは便!便秘はご法度
- 排泄をサポートしてくれる大切な短鎖脂肪酸。
それを産生してくれているのが腸内細菌。腸内細菌の乱れは短鎖脂肪酸の乱れに直結。
- バランスの良い食事を摂ることが鍵
腸内細菌が支える
腸の働き その3
2021/02/20
腸の働きには大きく7つあります。
その7つの働きとは、「合成」、「消化」、「吸収」、「排泄」、「解毒」、「浄血」、「免疫」です。
それを1つ1つ探っていきます。
今回は腸の働きの吸収についてお話ししていきます。
腸の働き 「吸収」
栄養素の入り口となる小腸。
長さは約6mあり、表面は絨毛と呼ばれる無数の突起があります。
絨毛と言う名のとおり、家庭に敷いてある毛が長く輪っかになっている絨毯を想像してください。
この表面から栄養が吸収されていきます。
ここからがすごいところです。
ただ、やみくもに栄養素が吸収されるわけではありません。
グルコース(糖)やアミノ酸など、それぞれの入り口があります。
水ですら専用の入り口があるのです。
ですから、体内に必要とされない栄養や異物は取り込まれないようになっています。
そして不要なものは体外に排出されます。
細菌やウィルスといった、外敵から身を守る免疫システムが備わっているのです。
この選別機能が機能不全を起こしてしまうと、必要な栄養素が取り込まれなかったり、有害物質を排出できなくなります。
体にとっては一大事です。
この機能を正常に保っておくために必要なのが腸内細菌です。
近年よく耳にする『リーキーガット証拠群』。
腸粘膜に穴が開き、腸から栄養や腸内細菌、病原菌などが体内にあふれでてしまうことをいいます。
これは、腸内細菌が十分に機能していないために穴が開いてしまうと言われています。
リーキーガット症候群になると、栄養素は消化不十分の大きな分子のまま腸管から体内に流出しやすくなります。
このようなことが原因不明の体調不良であったり、食物アレルギーの原因とも考えられています。
からだに不調を与えないためにも、腸内細菌を増やして丈夫な腸粘膜をつくることが必要になります。
腸内細菌や腸粘膜を痛めつけてしまうような、抗生物質や食品添加物、化学物質など不用意に体内に取り入れないが大切です。
体のためにとサプリメントを多く摂取している方もいらっしゃいますが、そのサプリメントの栄養素が化学的に作られたものではありませんか?
また、大量の飲酒も要注意ですし、亜鉛などのミネラルの不足も、腸粘膜に穴が開きやすくなりますから気をつけましょうね。
腸内細菌が支える
腸の働き その2
2021/02/18
腸の働きには大きく7つあります。
その7つの働きとは、「合成」、「消化」、「吸収」、「排泄」、「解毒」、「浄血」、「免疫」です。
それを1つ1つ探っていきます。
今回は腸の働きの消化についてお話ししていきます。
腸の働き 「消化」
消化の段階は食べ物で異なります。
お米やパンなどの炭水化物は、口の中の唾液と絡んだ時から、唾液の消化酵素アミラーゼによって分解がスタートしています。
肉や魚などのタンパク質は、胃に届いてからはじめて分解がスタートします。
胃では分解作業以外に、外から食べ物などと一緒に入ってきた病原菌を消毒、殺菌します。
胃の中で柔らかくなった食物は、十二指腸に送られます。
十二指腸が消化の要です。
十二指腸では、すい臓や胆のうから分泌される消化酵素と胆汁によって、食べ物はさらに細かく細かく分解されます。
脂質はここで初めて分解がスタートします。
十二指腸でしっかりと分解が行われ、空腸、回腸に送られ、食べ物が最終単位へと分解、消化されます。
この流れをたどっても臓器では消化できないものがあります。
それが食物繊維です。
その食物繊維を分解してエネルギー源の短鎖脂肪酸にしてくれているのが腸内細菌です。
胃でもすい臓でも消化できないために最終的に腸内細菌が助けてくれています。
だから、せっかく食べた物(栄養素)をしっかり体に満たしてあげるためには、各消化器官と腸内細菌が働きやすい環境を意識してあげる必要があります。
各消化器官を労わってあげる簡単な方法は、まず、よく噛んで食べることです。
口で細かくよく噛めば噛むほど唾液の分泌量が増えて、消化をサポートしてくれる酵素や、活性酸素を消去する酵素も含まれているので老化防止にもつながります。
さらに、食事と食事の間隔をしっかりとることです。
消化には5〜8時間かかり、消化の悪い食べ物だと10時間以上かかることがあります。
だから、毎日とは言いませんが、週に1回は最後の食事から次の食事まで16時間空けてしっかりと消化器官を休ませてあげるといいですね。
その際、お白湯はとって大丈夫です。
空腹は最高のアンチエイジングともいいますから、ぜひ日常生活に取り入れてみてください。
- 炭水化物(米・パン・麺など)は口に入れたときからアミラーゼによって分解・消化がスタート
- タンパク質(肉・魚・大豆など)は胃に届いてから胃液(ペプシン)よって分解・消化がスタート
- 脂質(油)は十二指腸に届いてから胆汁やリパーゼによって分解・消化がスタート
- 食物繊維は大腸に届いて腸内細菌によって分解・消化がスタート
- 週に1回は食事と食事の間を16時間空けて各消化器官を休めてあげる
腸内細菌が支える
腸の働き その1
2021/02/17
腸は、小腸と大腸からなり、長さは7〜8mもあります。
その中には100兆個もの腸内細菌がいます。
その腸内細菌と力を合わせて腸は様々な働きをしています。
消化吸収だけでしょ?と思っていませんでしたか?
うんちを作り出すところとだけ!と思っている人もいるかもしれません。
だから、便秘になったら下剤を飲めばいいでしょ。
安直に考えがちになります。
でも、それは仕方がないこと。
腸の素晴らしい働きを知らないから。
ぜひ、この機会に腸の素晴らしい働きを知って、ツヤツヤ、ハツラツ、元気な体を手にいれましょう!!
腸の働きには大きく7つあります。
その7つの働きとは、「合成」、「消化」、「吸収」、「排泄」、「解毒」、「浄血」、「免疫」です。
それを1つ1つ探っていきます。
- 酵素
「酵素」って聞いたことありますよね。
酵素は生命を維持するのに欠かせないものです。
代表的なものに「消化酵素」があります。
食べた物を栄養素に分解してくれます。
この酵素は腸と腸内細菌が協力して作り出しています。
私たちの酵素では消化分解できない食物繊維も、腸内細菌は分解できる酵素を持っている菌がいるので、その菌の力をかりています。
酵素ドリンクなど、数年前にかなり流行った記憶があります。
でも、残念ながら食品から摂ろうとしても加熱してしまうとその働きは失われますし、生で摂っても胃酸でやられてしまいます。
栄養にはなりますけど、酵素として体内で機能することはできません。
つまり、「酵素」は腸と腸内細菌をメインに作り出してもらうしかないのです。
だから、腸が活発に元気に働いてくれるように腸内環境にしておく必要があります。
- ビタミン
体のだるさや肌艶などの改善のためにビタミンを摂ろうと、サプリメントなど摂取した経験がありませんか?
ショコラBBとか有名ですね。
そんなビタミンも腸内細菌が作っているのです。
ビタミンB1、B2、B6、B12、パントテン酸、ナイアシン、ビオチン、ビタミンK、葉酸を合成する能力があります。
ビタミンB1は糖質の分解を助けてくれます。
不足すると、むくみや肩こりがおこりやすくなります。
ビタミンB2は健康な肌をつくってくれます。
不足すると口内炎、肌荒れをおこします。
腸内細菌はこうした大切なビタミンを合成してくれます。
だから腸内細菌が乱れるとビタミンの合成がうまくいきません。
腸内細菌が乱れれている中で一生懸命にサプリメントを摂取しても効果が出るのが疑問です。
乱れていなければサプリメントを摂る必要もないですね。
- ホルモン
ホルモンは、情報伝達物資です。
体の内外で起きていることを各器官に伝えて、それぞれの機能を誘導します。
例えば、インスリンです。
食事をとることでインスリンが分泌されます。
これは血糖などを一定に保とうとする働きです。
十二指腸でつくられるセクレチンやコレシストキニン。
小腸がつくるインクレチン。
これら消化管ホルモンは、消化のための様々な指令を各器官に伝えています。
腸は、消化に関わるホルモン以外にも重要なホルモンを作る場でもあります。
それは「幸せホルモン」と言われているセロトニンです。
セロトニンは脳内情報伝達物資ですが、体全体のセロトニンの90%は腸にあります。
脳にはたったの2%としかないそうです。
セロトニンが不足してしまうと、やる気がでなかったり、うつ状態になってしまったりします。
セロトニンは腸にあるEC細胞で作れています。
腸内細菌がこの合成に関係しています。
腸内細菌はこれらを合成するための材料を提供しているのです。
腸内環境を整えることで精神の安定にも繋がります。
- その他
その他多くの物質が腸内で作られています。
それらすべてに腸内細菌が関与しています。
腸の蠕動運動を刺激したり、細胞のエネルギー源となり、病原菌毒素から腸を守る短鎖脂肪酸やアンチエイジング成分のポリアミン、抗酸化作用のある水素も腸内細菌が作っています。
- 酵素の合成
- ビタミンの合成
- ホルモン合成
- その他、アンチエイジング成分、抗酸化作用のある水素
花粉症の症状が出る前にこれをやっておこう!
アーユルヴェーダで花粉症とさようなら
2021/02/16
春はすぐそこまで来ています。
朝晩はまだまだ寒いですが、カパの季節が到来しつつあります。
カパの季節は、外気に水が増えます。
人の体にも水がたまりやすくなります。
結果、肺から上の部分にカパが蓄積し、花粉症が発症しやすくなるといわれています。
花粉症の私は、アレグラを飲み、痒みを止めの目薬を点眼してと、苦労しています。
不本意ながら薬漬けになってしまう時期です。
カパの原理を知っているのに、ついつい生活習慣を改めなかった結果が…
薬に頼ってしまうはめに。
花粉症の症状を緩和することができたのにー(涙)
毎年後悔しています。
カパを減らすには、まず1月の寒い季節からしっかりと運動をすること。
カパを減らす味の一つは辛味です。
これも1月〜2月ごろから積極的に取り入れるといいです。
辛味のスパイスの代表格は、ショウガ、黒コショウ、ヒハツです。
この3つの辛味のスパイスの総称をトリカトゥといいます。
この3つのスパイスを同量混ぜ、1日2回、小さじ半杯をはちみつと混ぜて摂ります。
鼻水、くちゃみ、鼻づまりなどの花粉症の症状が驚くほど緩和されます。
ただし、症状が出てからでは効果が薄いので、症状が出る前から摂ると効果があります。
カパが増加するということは、消化力の低下が低下してい状態です。
消化力が低下していると体内に毒素が溜まりやすくなります。
この体内に溜まった毒素が花粉症を誘発しやすくすると考えられます。
だから、消化力を高めて、体内の毒素を溜めにくい体にすればいいのです。
体内の毒素を出してくれるオススメスパイスはフェンネル。
このフェンネルに、ジンジャーパウダー、クミンパウダー、コリアンダーパウダーを2:1:1:1の割合で摂ります。
小さじ1杯分くらい摂るといいので、そのまま一気に流し込むもよし、料理に加えてしまうのもよしです。
体内の毒素が消化されるので、花粉症を緩和しますよ。
上を向いて空を見上げて!!
2021/02/15みんな〜最近、空見上げてるー?


見上げよう!!
空を見上げて肩の力を抜こう。

丁寧に生きるとはどういうことなの?
2021/02/14丁寧にいきるとはどういうことか、私なりに深堀してみます。
丁寧に生きるにはどうしたらいいのか。
ずばり、心に素直でいること。
少しでも自分の心に違和感を覚えたら、その違和感と向き合いましょう。
向き合わずに、その違和感に蓋をしてしまい、なかったことにしてしまう。
そんな繰り返しをしていると、ボディブローのように後からジワジワダメージが。
自分では気づかないうちに心が破壊されていきます。
このうように徐々に心にダメージを与えてしまって、気が付いたらうつ病になっていたと言う人も多いいように感じます。
ちょっとした心の違和感に向き合うと、それを解消すべく行動が伴ってきます。
素直に心で感じ、体で動く。
丁寧に生きるとはそういうことだと私は思います。
所作にしても、心でガサツな自分が嫌だと感じるから、ゆったりとした仕草に変えようと行動に移します。
ここで、ガサツな自分が嫌いだと感じているだけで終わっていると、丁寧に生きることはできません。
整理整頓された部屋にしたいと心で感じているから、散らかっている部屋を見てイライラ。
この心としっかり向き合えば、生理整頓された部屋にするための行動に移せます。
断捨離して美しいお花を部屋に飾るかもしれませんよね。
自分の体に対しても同じ。
もし、太っている自分が嫌で仕方がないと感じているとしたら、太ってしまった原因に対して向き合うようにしてほしい。
その原因と向き合わなければ、一生自分を好きになることはできない。
こうして、心で感じたちょっとした違和感と向き合うことが、丁寧な生き方になっていきます。
ちょっとした心の違和感といちいち向き合っていたら、時間がいくらあっても足りないと思うかもしれません。
しかし、大なり小なり感じたことを覚えている時に向き合わなければ、もっと時間がかかることになりますよ。
私の自己嫌悪の塊という闇はかなり奥深く…もっとこまめに向き合っていれば良かったなと今更思ってますから。
ただ、言い訳させてもらうと、「心と向き合うことをしなければいけない」なんてことを知らなかった。
自然と幼いころからそれができる人も多くいるでしょう。
でも、自分の心と向き合うことをせずに、私のように自己嫌悪の塊を作ってしまった人も多くいるはず。
生きずらさを感じているなら、今からでも遅くない。
じっくりと時間をかけて、自分に対して丁寧に生きてほしい。
自分に対して丁寧に生きれることで、他人に対しても丁寧に接することができるし、日常生活も丁寧に生活できるはずです。
もし、雑に生きていると気が付いた方は今から、丁寧に生きる努力してください。
それが、あなたの幸福への近道です✨
丁寧に生きる
自分が大嫌い!からの脱却
2021/02/13
丁寧に生きていますか?
丁寧とは『細かいところまで気を配ること。注意深く入念にすること。言動が礼儀正しく、配慮が行き届いていること。』とデジタル大辞泉に書かれています。
このように生きてますか?
丁寧に生きることで何が変わるのでしょうか?
私は、自分を好きになることができました。
イライラから解放されました。
雑に生きているつもりなんて全くなかったけど…
むかしむかし、知人に「雑に生きてますねー、もっと自分を大切にしてください」と言われました。
その時は、何言ってるのかさっぱり意味不明でした。
だって、私はただ普通に生きていたから。
生きるのに丁寧も雑もあるのか?
でも、その言葉を忘れることができずにいました。
私は、自己嫌悪の塊で、「私なんて」という意識が強くありました。
この意識こそ雑に生きてきた証だったのだとわかったのは
もう何年も後のこと。
丁寧に生きることは、自己嫌悪感を減少させてくれます。
結局、やることなすこと雑にやっていて、一つ一つのことにしっかりと向き合ってこなかったことが、自己嫌悪の塊の私をつくりだしていたのです。
雑に生きてきたからこそ、やることなすこと中途半端な自分と感じてしまって、自分が嫌いだったのです。
自分で自分を許せるくらいに丁寧に生きたら、少し堂々と振る舞えるようになります。
自分で納得できる自分なることができます。
もし、今の自分が大嫌いで自己嫌悪の塊で生きづらさを感じている人は、一度、丁寧に生きてみることを意識してみてください。
次回は、丁寧に生きることをもう少し深堀していきたいと思います。
脂肪を燃やすてっとり早い方法は?
2021/02/10空腹で就寝すること!!
なぜかというと、脂肪は安静時の筋肉代謝で燃えます。
だから寝ている間に脂肪は燃えているのです。
ただし、インスリンの分泌が止まり血糖値が下がっている状態での就寝が条件です!!
そのために重要なポイントは、『インスリン機能を改善する』、脂肪を燃やすための『筋肉量を増やす』です。
人は食事をすると、血糖値が上昇しインスリンが分泌されます。
インスリンが血糖値を十分に低下させると、インスリンの分泌が止まります。
その後、脂肪の分解が始まります。
しかし、インスリンの抵抗性があると血糖値がいつまでも低下せず、脂肪は燃え始めません。
そのため、インスリン抵抗性を改善することが大切になります。
インスリン抵抗性を改善させる方法は、ズバリ「断食」です。
体の機能改善のために断食は有効なのです。
ただ、3日も4日も何も食べない「断食」をする必要はないです。
最後に摂取した食事から、次にとる食事を16時間空けるだけの「間欠断食」でいいのです。
これで、インスリン抵抗性は改善されます。
インスリン抵抗性が改善されて、正常に脂肪が燃えることができます。
筋肉を増やすことでもっと燃えやすくなるので、筋トレと間欠断食を習慣にとり入れてみませんか。
テレワークで人に会わないからといって、歯磨き怠っていませんか?
2021/02/06
テレワークで人に会わないからといって、歯磨き怠っていませんか?
そのまま放置しておくと、大変なことになるかもしれませんよー!!
みなさんは、口の中の歯垢を採取して顕微鏡で見たことありますか?
私はあります!
お世話になっている歯科では、見せてくれるのです。
これ本当にびっくりしますよ。
ウジャウジャいますから〜。
細菌とやらが!!
細菌がいるのは当たり前なのですが(笑)
口腔内には約700種類の細菌がいると言われていますから。
唾液を飲み込むたびに、食事をするたびに、その最近を飲み込んでいることになりますから。
安心して下さい。
飲み込んだ細菌の大部分は胃酸で処理されますから。
ただ、残念なことに歳と共に胃酸の分泌は低下していきます。
そのために、歳と共に多くの細菌が胃を通過してしまうのです。
しかし、口腔内細菌と私たちは共生関係にあります。
口腔内の環境保全のためにも細菌は必要なものです。
共生細菌のおかげで、口腔内の粘膜が保全されていたり、歯の表面に口腔内細菌を付着させておくことで、他の病原菌が付着するのを防いでいたりしてくれています。
でも、口腔内の環境が悪く、細菌が平均より増殖してしまっている状態だと、最終的に腸内環境にまで影響をおよぼしてしまいます。
そのありがたい共生細菌が生存しにくい環境を引き起こしてしまう要因が、食べ物!
そして、タバコとお酒。
砂糖はもっとも口腔内環境を悪化させます。
これは、子供のころチョコレートべたら虫歯になるよって言われていたからなんとなくわかっていることですよね。
なぜ砂糖が悪いかと言うと、口腔内細菌は砂糖を発酵して乳酸などの酸をつくってしまって歯を溶かしてしまうから。
どんどん酸性に傾いていくと、歯周病になってしまう。
最終的に病気のオンパレード!!
腸内環境にまで影響をおよぼします。
誤嚥性肺炎、脳梗塞・心筋梗塞、骨粗しょう症、細菌性心内膜炎、早産・低体重出産、糖尿病・肥満、高血圧や高脂血症、腎炎、関節炎、皮膚疾患など、自身の命に関わるものから、胎児に影響するものまで多大な健康被害の元凶にも。
だから口腔内のケアは怠ってはいけない。
セルフケアは、毎日の歯磨き、歯間ブラシとともに、舌磨きとオイルプディング。
オイルプディングと舌磨きについてはこちら
あとは、定期的に歯科でクリーニングを受けることをオススメします。
人に合わないからいいや!マスクしてるからいいや!と歯磨きしないでいると大変なことになりますからね。
気を付けましょうね。
生活の積み重ねで今の私の体がつくられている
2021/02/04前回、免疫力を下げないために日光浴をしましょう。
ビタミンDが免疫力に必要ですよというお話しをしました。
そもそも、なぜ免疫機能は低下してしますのでしょうか?
何年か前に「癌は生活スタイルを変えることで予防できる」という論文が、アメリカのMDアンダーソン癌センターから発表されました。
アメリカではトップの癌センターだそうです。
癌は遺伝的要素が高い疾患であると考えられていました。
癌検査をすると必ず問診に、親族に癌の人はいますか?とありますよね。
でも、遺伝的要素がゼロではないが、親族に癌の人がいなくても自分だけ癌になったという話も聞きます。
この論文では、癌は生活習慣病であり、その90〜95%は生活スタイルを変えることで予防ができるという内容です。
免疫力の低下が癌発症原因であるとしたら、癌を予防するため、免疫機能を上げることであると考えられます。
今はコロナ感染予防のために免疫力アップに努めている方は必然的に癌予防にもなっているでしょう。
では、生活スタイルを変えるとはどうしたらいいのか?
私のブログを読んでくれてる方には、もう耳にタコができるくれい聞いていますね。
そうですよー!
食事、運動、睡眠、ストレスケアを全て見直すことです。
添加物たっぷりのジャンキーなもの食べてませんか?
運動してますか?
最低でも6時間は寝ていますか?
ストレスをため込んで我慢していませんか?
ひとつひとつ見直して、行動できることから改善していきましょう。
日光浴でこの危機を乗り切りろう!!
2021/02/02今だからこそ、日光浴を毎日10分〜15分すべきです。
日の光を皮膚に浴びることで、皮膚に蓄積されているコレステロールを原料として『ビタミンD』という物質が作られます。
ビタミンDは、リンパ球やマクロファージと呼ばれる白血球の機能をコントロールしています。
ビタミンD不足の状態では感染症にかかるリスク、重症化するリスクが高まってしまします。
だから、体内のビタミンD濃度が高い状態を維持できている人が、この危機を乗り切れると言えます。
その、ビタミンD濃度を高める方法が日光浴なんです。
太陽の光を浴びるだけで、ビタミンDが上昇して免疫力があがるのですから、日光浴を断固拒否します!!なんてことにはなりませんでしょ。
毎日の日光浴が体内にビタミンDを蓄積させてくれます。
夏は5分、冬は15分程度、朝日から昼までの日の光を浴びるようにしてください。
女性はどうしても日焼けをしたくないので、日焼け止めを使用していると思います。
日焼け止めを塗布していると効果は落ちてしまいます。
日焼けしてもあまり気にならない手のひらを太陽に!!
手のひらを太陽に すかしてみれば
まっかに流れる ぼくの血潮〜
それに加えて、ビタミンDを含む食品を積極的に食べるようにしましょう。
焼き鮭、うなぎのかば焼き、さば水煮缶、きのこ類、鶏卵、レバー類、チーズ、バター
抗がん、認知症予防、慢性疲労改善、うつ病改善、糖尿病予防、男性機能向上、などの効果もしめされています。
さぁ、日光浴でこの危機を乗り切ろう!!
-
 休んでいるのに疲れが抜けない理由
休んでいるのに疲れが抜けない理由― 回復できない体の仕組み ―「しっかり休んでいるはずなのに疲れが取れない」こ
休んでいるのに疲れが抜けない理由
休んでいるのに疲れが抜けない理由― 回復できない体の仕組み ―「しっかり休んでいるはずなのに疲れが取れない」こ
-
 健康は数値だけでは測れない
― 心・体・魂の調和というアーユルヴェーダの健康観 ―病院の検査で「異常はありません」と言われたにもかかわらず
健康は数値だけでは測れない
― 心・体・魂の調和というアーユルヴェーダの健康観 ―病院の検査で「異常はありません」と言われたにもかかわらず
-
 花粉症は「体内環境の乱れ」から始まる 1
花粉症は「体内環境の乱れ」から始まる花粉症は一般的に「免疫の過剰反応」と説明されますが、Ayurvedaではさ
花粉症は「体内環境の乱れ」から始まる 1
花粉症は「体内環境の乱れ」から始まる花粉症は一般的に「免疫の過剰反応」と説明されますが、Ayurvedaではさ
-
 「これだけ健康にも美容にも気を配ってきたのに、なぜ疲れが抜けないのか」
「これだけ健康にも美容にも気を配ってきたのに、なぜ疲れが抜けないのか」50代の女性から、非常に多くいただくご相
「これだけ健康にも美容にも気を配ってきたのに、なぜ疲れが抜けないのか」
「これだけ健康にも美容にも気を配ってきたのに、なぜ疲れが抜けないのか」50代の女性から、非常に多くいただくご相
-
 「アーユルヴェーダとは何か ― 心・体・魂を本来の調和へ戻すインドの伝統医学」
「アーユルヴェーダとは何か ― 心・体・魂を本来の調和へ戻すインドの伝統医学」最近、「しっかり寝ているのに疲れ
「アーユルヴェーダとは何か ― 心・体・魂を本来の調和へ戻すインドの伝統医学」
「アーユルヴェーダとは何か ― 心・体・魂を本来の調和へ戻すインドの伝統医学」最近、「しっかり寝ているのに疲れ
いつも当サロンをご利用いただき、誠にありがとうございます。
本日より、2月分の予約受付を開始いたしましたのでお知らせいたします。
2月は日数が短いため、例年週末を中心に予約が埋まりやすくなっております。
ご希望の日時がある方は、お早めのご予約をおすすめいたします。
平川ふゆ
新年あけましておめでとうございます!
旧年中は サロンドラヴィナをご愛顧いただき、誠にありがとうございました。
たくさんのお客様の笑顔に支えられ、素晴らしい一年を過ごすことができました。
2026年も、皆様にとって心からリラックスできる「癒やしの場所」であり続けられるよう、心を込めてお手入れさせていただきます。
また皆様にお会いできるのを楽しみにしております!
平川ふゆ
「年末年始はどうせ休みでしょ?」
そう思っている方へ。
当店は年末年始も通常営業です。
正月太りをつくらない。
生活リズムを崩さない。
いつも通り、淡々と身体を整える。
【1月の営業スケジュール】
1月1日
▶ 加圧トレーニングのみ対応
1月2日〜4日
▶ 通常営業(年末年始も通常通り)
1月10日〜11日
▶ 研修のため休業
1月19日〜26日
▶ 休業
1月は変則営業があります。
来店前に必ずカレンダーをご確認ください。
✨12月のお休みのお知らせ✨
いつもご利用いただきありがとうございます。
📅【休業日】
・毎週 月曜日・木曜日
・24日土曜日、25日日曜日は研修のためお休みをいただきます。
🕊ご予約について
・一般予約を開始いたしました。
・オンラインカウンセリング(マインドケアセラピー) は夜18時以降も受付中です。
・初めての方は 30分無料オリエンテーション をぜひお気軽にご利用ください。
皆さまにお会いできることを楽しみにしております💐
🌿1日2名様限定・完全予約制
ご希望日時がある場合は、お早めのご連絡をおすすめいたします。
空き状況は下記をクリック カレンダーをご確認ください。