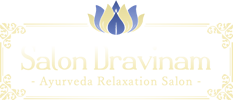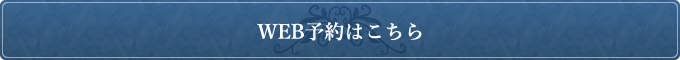- ホーム
- "a more fulfilling life" ブログ
"a more fulfilling life" ブログ
1週間で試すバランスを取るための小さな習慣10選
2025/03/30
忙しい日々の中で、心と体のバランスを取ることはとても大切です。
しかし、大きなライフスタイルの変化をするのは難しいもの。
そこで、今回は1週間で簡単に取り入れられる小さな習慣をご紹介します。
これらの習慣は、少しの意識と実践で無理なく続けられるものばかり。
毎日少しずつ試していくことで、健康的で心地よい生活に近づくことができます。
「健康のために何か始めたいけど、何から手をつけたらいいかわからない」「毎日が忙しくて時間が取れない」という方でも、気軽に取り組めるアイデアばかりなので、ぜひ1つでも取り入れてみてください。
それでは、1週間で試せるバランス習慣10選を見ていきましょう!
1週間で試すバランス取るための小さな習慣のアイデア
日常生活に簡単に取り入れられる小さな習慣は、健康を保ち、バランスを取るために非常に効果的です。
1. 朝のストレッチ
朝起きたら、まず3分間だけストレッチをすることから始めましょう。
体を目覚めさせる短い時間のストレッチは、血液循環を良くし、一日の活動をスムーズにします。
特に肩や首をほぐす動きを意識すると良いです。

2. 毎日の水分補給
朝起きてすぐ、コップ1杯の水を飲む習慣を取り入れてみてください。
これは、体をリフレッシュさせるだけでなく、消化を助ける役割も果たします。
また、食事の際に水を飲むことで、満腹感が得やすくなり、食べ過ぎを防ぐことにもつながります2。

3. 定時の食事
朝食、昼食、夕食を規則正しく摂ることを心掛けましょう。
決まった時間に食事を取り、食事中はスマホやテレビを見ずに味わうことで、満足感が得られ、暴飲暴食を避けることができます。

4. 日記をつける
自分の行動を日記に記録してみるのも有効です。
毎日、何を食べたのか、どのくらい運動したのかを書き出すことで、自分の健康状態に対する意識が高まります。
手書きの日記やアプリを使って記録する方法もあります。

5. 短時間の運動
毎日10分程度の軽い運動を取り入れることも習慣化しやすいです。
家の周りを歩いたり、ストレッチや簡単な筋トレを行ったりすることで、基礎代謝が向上し、心身ともにリフレッシュされます。

6. 適切な睡眠環境の整備
毎晩同じ時間に寝ることを心掛け、睡眠環境を整えましょう。
寝る前1時間は、スマホの使用を避けてリラックスできる時間を設けることで、質の高い睡眠が得られます。
これにより、日中のエネルギーレベルが向上します2。

7. 一日の振り返り
夜寝る前にその日の出来事を振り返る時間を持ちましょう。
良かったことや改善点を書き出すことで、自己反省を行い、次の日をより良く過ごすための意識を高めることができます。
これも心の健康にプラスとなります。

8. デジタルデトックス
毎日一定の時間、特に就寝前の1時間は、デジタル機器から離れることを意識しましょう。
これによって、目の疲れを軽減し、より良い睡眠が促進されます。この習慣は、ストレス管理にも効果的です。

9. ヘルシーな間食を選ぶ
間食の際に、ナッツやフルーツ、ヨーグルトを選ぶことで、一日を通したエネルギーのバランスを崩さないようにできます。
また、糖分が高いスナックを避けて、栄養価の高い食事を心掛けましょう。

10. マインドフルネス
毎日数分間、深呼吸や瞑想を行うことで、ストレスを軽減し、心を落ち着ける時間を持ちましょう。
これは感情の安定にも寄与し、仕事や日常生活のパフォーマンス向上につながります。
どれか1つでも、気になるものから始めてみてくださいね♡
#アーユルヴェーダの理念 #バランスのある暮らし #心と体の調和 #ライフスタイル改善
お腹の脂肪を減らす!アーユルヴェーダ的アプローチ⑭
「まとめ&実践計画」
2025/03/28

これまでのシリーズで、アーユルヴェーダの知恵を活かした「お腹の脂肪を減らす方法」について詳しくお伝えしてきました!
最終回となる今回は、重要なポイントの振り返りと、すぐに実践できる3ステッププランをご紹介します!
~14回のポイントを振り返る~
- アーユルヴェーダ的にお腹の脂肪を減らす基本ルール
- 体質(ドーシャ)に合ったアプローチを取ることが大切!
- 消化力(アグニ)を高め、脂肪が溜まりにくい体をつくる!
- ストレスや生活習慣を整え、脂肪燃焼しやすい環境をつくる!
各回の重要ポイントまとめ
- アーユルヴェーダ的に脂肪を減らす考え方(第1回・2回)
☆ 体質(ドーシャ)や消化力(アグニ)を整えることがカギ!
- 体質別の脂肪対策(第3回~5回)
☆ヴァータ:温かい食事&リラックスが大事
☆ ピッタ:冷やしすぎに注意し、適度な運動を
☆ カパ:刺激的な食べ物&アクティブな生活が◎
- ハーブ・デトックス・ヨガで脂肪燃焼!(第6回~8回)
☆ ググル・トリファラ・ターメリック などのハーブで脂肪燃焼をサポート
☆ パンチャカルマ(デトックス) で体内をクリアに
☆ 舟のポーズ・ねじりのポーズ でお腹周りを引き締める
- 日々のルーチン&食事管理(第9回~11回)
☆朝の白湯・適度な運動・規則正しい食事が大切
☆6つの味(辛味・苦味・渋味など) をバランスよく摂取
☆ ハニージンジャーティーやクミンウォーターで代謝アップ!
- ストレス管理と運動習慣(第12回~13回)
☆ストレスが脂肪の蓄積を招くため、リラックスが重要
☆ 有酸素運動と筋トレの組み合わせが◎
☆ 短時間で効果的な「加圧トレーニング」 もおすすめ!
実践しやすい3ステッププラン
「知識は身についたけど、何から始めればいいかわからない…」という方は、まずこの3ステップから始めてみましょう!
ステップ1:朝のルーティンを整える
- 起床後すぐに白湯を飲む(消化力UP&デトックス)
- 軽いストレッチやヨガをする(体を温め、代謝UP)
- 食事前にハーブティーを飲む(消化を助ける)
まずは1週間続けてみることが大切!
ステップ2:食事のリズムを整える
- お腹が空いたら食べる(間食を減らす)
- 6つの味を意識したバランスの良い食事を摂る
- 夜遅い食事や冷たい飲み物を避ける
「夜7時以降は食べない」だけでも効果あり!
ステップ3:適度な運動を習慣化する
- 週に2〜3回は有酸素運動+筋トレを行う
- 短時間で効果が出る「加圧トレーニング」を試す
- 日常生活の中で「ながら運動」を取り入れる(通勤時に階段を使う、家事の合間にスクワットなど)
「まず10分だけ!」と決めてやるのがコツ!
継続するためのモチベーション管理
「続けられるか不安…」という方のために、モチベーションを維持する方法をご紹介します!
- 目標を設定する
・例:「1ヶ月後にウエストを2cm減らす!」
- 記録をつける
・体重・ウエストサイズ・食事・運動の記録を残すと、達成感が得られやすい!
- 仲間を作る
・友人や家族と一緒に取り組むと、継続しやすい!
- ご褒美を設定する
・1ヶ月続けたら「新しい服を買う」「マッサージに行く」など、自分にご褒美をあげる
「完璧を目指さない!」も大切。続けることが何より重要です!
まとめ:アーユルヴェーダの知恵を活かして、お腹の脂肪を減らす!
- 体質(ドーシャ)に合った食事・運動・生活習慣を取り入れる!
- 消化力(アグニ)を高め、脂肪燃焼しやすい体をつくる!
- ストレスを減らし、健康的な生活リズムを整える!
「やってみよう!」と思ったら、まずは3ステッププランからスタート!
短時間で効果を実感したい方へ!加圧トレーニングの無料体験受付中!!
「運動が苦手」「短時間で効率よく脂肪を燃やしたい!」 という方におすすめの 加圧トレーニング 。
初めての方には無料体験をご用意しています!
サロンページからご予約ください!!
スペシャルメニューでは「体質改善3ヶ月プログラム」もご用意しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
ご不明な点がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
お腹の脂肪を減らす!アーユルヴェーダ的アプローチ⑬
「おなかの脂肪を減らすための運動」
2025/03/27

お腹の脂肪を減らすために「運動しなきゃ!」と思っても、どの運動が効果的なのか迷ってしまうことはありませんか?
アーユルヴェーダでは、運動は体質(ドーシャ)や消化力(アグニ)に合ったものを選ぶことが重要と考えます。
今回は、お腹の脂肪を減らすためのアーユルヴェーダ的な運動の考え方と、短時間で効果的な「加圧トレーニング」の魅力をご紹介します!
アーユルヴェーダ的な適度な運動
アーユルヴェーダでは、運動は「バランスを取るための手段」と考えます。
過度な運動はストレスや消化不良を招くため、心地よくできる運動を習慣にすることが大切です。
- 体質別のおすすめ運動
| 体質(ドーシャ) | おすすめの運動 | 避けた方がよい運動 |
|---|---|---|
| ヴァータ(風) | ヨガ・ストレッチ・ウォーキング | 激しいランニング・ハードな筋トレ |
| ピッタ(火) | 水泳・軽めのランニング・サイクリング | 極端な競争スポーツ |
| カパ(水) | ダンス・HIIT・ジョギング・筋トレ | 動きの少ない運動(ストレッチのみ) |
※ ポイント:カパ体質の人は脂肪をためやすいので、やや強度の高い運動を習慣にする。
有酸素運動 vs 筋トレ:どちらが脂肪燃焼に効果的?
お腹の脂肪を減らすには、有酸素運動と筋トレのバランスが大切です!
有酸素運動のメリット
- 脂肪を燃焼しやすい
- 心肺機能が向上し、血流を改善
- ストレスを和らげる
おすすめの有酸素運動
- ジョギング(週3〜4回、30分程度)
- ダンスやズンバ(楽しく動ける!)
- ウォーキング(食後30分以内が◎)
筋トレのメリット
- 基礎代謝が上がり、脂肪が燃えやすい体になる
- 姿勢が整い、お腹周りが引き締まる
- 体のバランスを整え、ケガの予防になる
脂肪燃焼には「筋トレ→有酸素運動」の順番が効果的!
短時間で効果を出すなら「加圧トレーニング」がおすすめ!
「運動したいけど、時間がない…」
「なるべく短時間で効率よく脂肪を落としたい!」
そんな方におすすめなのが 「加圧トレーニング」 です!
加圧トレーニングのメリット
- 短時間で脂肪燃焼:20分程度のトレーニングでも、通常の筋トレと同じ or それ以上の効果!
- 成長ホルモンが大量分泌:脂肪燃焼&美肌効果も◎
- 血流改善で代謝アップ:むくみや冷えの解消にもつながる
- 低負荷でできる:通常の筋トレより軽い負荷でOKだから、運動が苦手な人でも続けやすい
ポイント:加圧トレーニングは、脂肪燃焼・筋力UP・代謝向上を効率よく叶える「時短トレーニング」!
まとめ:無理なく運動を習慣化して、お腹の脂肪を減らそう!
- アーユルヴェーダ的な運動のポイント
・汗ばむ程度の運動を継続する
・体質(ドーシャ)に合った運動を選ぶ
- 酸素運動 vs 筋トレ
・脂肪燃焼には「筋トレ→有酸素運動」の順番が◎
・ウォーキングやジョギング+簡単な筋トレを取り入れる
- アクティブなライフスタイルの作り方

・朝のストレッチやヨガで代謝UP
・ながら運動を増やして、無理なく動く習慣を作る
・夕方のウォーキングでストレス解消&脂肪燃焼
- 短時間で効果を出すなら加圧トレーニング!
・20分程度のトレーニングでも高い脂肪燃焼効果
・成長ホルモンの分泌を促し、痩せやすい体に
・血流を改善し、代謝をアップ
初めての方には無料体験をご用意しています!
ぜひ、サロンページからご予約ください。
短時間でもしっかり結果を出せる加圧トレーニングを、ぜひ体験してみてくださいね!
次回は 「まとめ&実践計画」 をご紹介します!お楽しみに!
お腹の脂肪を減らす!アーユルヴェーダ的アプローチ⑫
「ストレスとおなかの脂肪の関係」
2025/03/26

ストレスがかかると「なぜかお腹周りに脂肪がつきやすくなる」と感じたことはありませんか?
アーユルヴェーダでは、心と体は密接につながっており、ストレスは消化力(アグニ)やホルモンバランスを乱し、脂肪の蓄積につながると考えます。
今回は、ストレスと脂肪の関係、そしてアーユルヴェーダ的なストレス対策について解説していきます。
ストレスが脂肪蓄積を引き起こす理由
1. コルチゾールの影響で脂肪がつきやすくなる
ストレスを感じると、体は「戦うか逃げるか」の状態に入り、副腎からコルチゾールというホルモンが分泌されます。
このコルチゾールは、エネルギーを確保するために 血糖値を上げ、脂肪を蓄積しやすくする 働きを持っています。
特に カパ体質の人はストレス時に脂肪をためやすい 傾向があります。
コルチゾールが増えるとこんな影響が…
- お腹周りに脂肪がつきやすくなる
- 食欲が増し、甘いものや揚げ物が欲しくなる
- 睡眠の質が低下し、代謝が落ちる

2. 消化力(アグニ)が低下し、未消化物(アーマ)がたまる
アーユルヴェーダでは、消化力(アグニ)が弱まると未消化物(アーマ)が体内に蓄積し、これが脂肪として体に残ると考えます。
ストレスがかかると、交感神経が優位になり、消化がスムーズに行われなくなります。
ストレスによる消化不良のサイン
- 食後に胃もたれ・膨満感を感じる
- 便秘や下痢を繰り返す
- 体が重く、疲れやすい
3. 不安やイライラで暴飲暴食しやすくなる
ストレスを感じると、心を落ち着かせるために 甘いものやこってりした食べ物を食べたくなる ことがよくあります。
しかし、これらの食事は脂肪の蓄積を助長し、さらにストレスの悪循環に…。
ストレス → 食べ過ぎ → 罪悪感 → さらにストレス → もっと食べる
このループを断ち切るためには、ストレスを根本から解消することが大切!
そこで、アーユルヴェーダ的なストレス対策を取り入れてみましょう。
ストレスを軽減するためのアーユルヴェーダ的アプローチ
1. 呼吸法(プラーナーヤーマ)で自律神経を整える
ストレスがたまったときは、深い呼吸を意識することが大切 です。
アーユルヴェーダでは、呼吸をコントロールすることで心を落ち着かせ、コルチゾールの分泌を抑えることができるとされています。
- おすすめの呼吸法:ナーディ・ショーダナ(片鼻呼吸法)
【やり方】
右手の親指で右の鼻を押さえ、左の鼻から息を吸う
右手の薬指で左の鼻を押さえ、右の鼻から息を吐く
これを1セットとし、5分ほど繰り返す
【効果】
- 自律神経を整え、リラックス効果UP
- 血流を促進し、代謝を活性化
- ストレスによる暴飲暴食を防ぐ
2. スパイスを活用してストレスを和らげる
ストレスが原因で消化力が弱まると、お腹の脂肪が燃えにくくなります。
そこで、アーユルヴェーダ的に消化を助け、心を落ち着かせるスパイスを活用しましょう。
- カルダモン → リラックス効果&消化促進
- フェンネル → 胃腸の働きを助け、膨満感を軽減
- ターメリック → 抗炎症作用があり、ストレスによる体の炎症を抑える
おすすめの飲み方
・カルダモンをお湯に入れてハーブティーに
・フェンネルシードを食後にかむ
・ターメリックミルクでリラックス
3. 夜の過ごし方を見直してストレス軽減
夜の過ごし方を工夫するだけで、ストレスによる脂肪の蓄積を防ぐことができます!
- 寝る前1時間はスマホを見ない → 睡眠の質がUP
- 温かいハーブティー(カモミール・ホーリーバジル)を飲む → 自律神経を整える
- セルフマッサージ(アビヤンガ)をする → オイルを使ってリラックス
特にアーユルヴェーダオイルを使ったセルフマッサージは、ストレス軽減&脂肪燃焼のサポートに◎
まとめ:ストレスを軽減すれば、おなかの脂肪も減らせる!
ストレスが脂肪をためる原因
- コルチゾールの分泌で脂肪が蓄積しやすくなる
- 消化力が低下し、未消化物(アーマ)が増える
- 不安やイライラが暴飲暴食を引き起こす
アーユルヴェーダ的ストレス対策
- 呼吸法(ナーディ・ショーダナ)で自律神経を整える
- スパイスを活用して心と消化を整える
- 夜の過ごし方を見直し、リラックス習慣をつくる
ストレスを減らせば、脂肪も減らせる!
次回は 「おなかの脂肪を減らすための運動」 をご紹介します!お楽しみに💛
お腹の脂肪を減らす!アーユルヴェーダ的アプローチ⑪
「おなかの脂肪を減らすための飲み物」
2025/03/25

アーユルヴェーダでは、消化力(アグニ)を高めることが脂肪燃焼のカギと考えられています。
今回ご紹介するのは、おなかの脂肪を減らすためのアーユルヴェーダ的ドリンク。
代謝を活性化し、脂肪燃焼をサポートする飲み物を日常に取り入れてみましょう!
①ハニージンジャーティー(はちみつ生姜茶)
代謝アップ & 消化促進
【材料】
・生姜スライス 2〜3枚(またはすりおろし小さじ1)
・お湯 200ml
・はちみつ 小さじ1(※熱湯ではなく少し冷めてから加える)
【作り方】
カップに生姜を入れ、お湯を注ぐ
↓
5分ほど蒸らした後、少し冷ましてからはちみつを加える
【効果】
- 生姜:消化力(アグニ)を高め、代謝を促進
- はちみつ:腸内環境を整え、脂肪燃焼をサポート
→ 特にヴァータ体質・カパ体質の人におすすめ!

②ターメリックミルク(ゴールデンミルク)
抗炎症 & 体を温める
【材料】
・ターメリックパウダー 小さじ1/2
・牛乳(またはアーモンドミルク) 200ml
・黒胡椒 少々
・はちみつ(またはギー)小さじ1
【作り方】
鍋に牛乳を入れ、ターメリックを加えて弱火で温める
↓
黒胡椒をひとつまみ加え、よく混ぜる
↓
火を止めて少し冷ましてから、はちみつを加える
【効果】
- ターメリック:炎症を抑え、脂肪燃焼を促す
- 黒胡椒:ターメリックの吸収を高める
- はちみつ / ギー:腸の健康をサポートし、代謝をアップ
→ 特にヴァータ体質・カパ体質の人におすすめ!

③クミンウォーター & フェヌグリークウォーター
デトックス & 消化促進
☆クミンウォーター(Cumin Water)
【作り方】
クミンシード 小さじ1を水300mlに入れる
↓
一晩浸けておく(または5分煮出す)
朝、空腹時に飲む
【効果】
- 消化力を高め、腸内環境を整える
- お腹の膨満感を減らし、脂肪の代謝を促す
- 特に ピッタ体質・カパ体質 におすすめ

☆フェヌグリークウォーター(Fenugreek Water)
【作り方】
フェヌグリークシード 小さじ1を水300mlに入れる
↓
一晩浸けておく(または5分煮出す)
朝、空腹時に飲む
【効果】
- 血糖値を安定させ、脂肪の蓄積を防ぐ
- 腸内環境を整え、便秘解消をサポート
- 特にカパ体質の人におすすめ!

まとめ:脂肪燃焼ドリンクで代謝アップ!
- ハニージンジャーティー → 消化力アップ&脂肪燃焼(ヴァータ・カパ向け)
- ターメリックミルク → 抗炎症&代謝促進(ヴァータ・カパ向け)
- クミンウォーター → デトックス&消化促進(ピッタ・カパ向け)
- フェヌグリークウォーター → 血糖値調整&脂肪燃焼(カパ向け)
次回は 「ストレスとおなかの脂肪の関係」 について詳しくお話しします!お楽しみに💛
お腹の脂肪を減らす!アーユルヴェーダ的アプローチ⑩
アーユルヴェーダ的ダイエットの基本ルール
2025/03/24

「食事制限してもなかなか痩せない…」
「運動してもお腹の脂肪が落ちにくい…」
そんなお悩みがある方におすすめなのが、アーユルヴェーダ的ダイエット。
アーユルヴェーダでは、「食べ方を間違えると太りやすくなる」「正しい食事の組み合わせで代謝が上がる」と考えます。
今回は、お腹の脂肪を減らすための基本ルールを解説します!
6つの味と消化の関係(ラサのバランスを整える)
アーユルヴェーダでは、食べ物の味(ラサ)が6種類あると考えます。
これらをバランスよく摂ることで、消化力(アグニ)が整い、脂肪燃焼をサポートします!
味 例 特徴
- 甘味(マドゥラ) 米、乳製品、ナッツ、熟した果物 体を滋養するが、摂りすぎると脂肪が増える
- 酸味(アムラ) ヨーグルト、レモン、発酵食品 / 消化を促進するが、摂りすぎると胃の不調につながる
- 塩味(ラヴァナ) 海塩、味噌、醤油 / 消化を助けるが、摂りすぎるとむくみの原因に
- 辛味(カトゥ) 唐辛子、生姜、胡椒 / 代謝を高め、脂肪燃焼を促進するが摂りすぎると胃や皮膚に負担がかかる
- 苦味(ティクタ) ゴーヤ、ケール、ウコン / デトックス効果があり、余分な脂肪を排出するが摂りすぎると冷えや乾燥が悪化
- 渋味(カシャーヤ) 緑茶、豆類、ザクロ / 体を引き締め、脂肪の蓄積を防ぐが摂りすぎると便秘や消化不良の原因に
ポイント
- 太りやすい人は甘味・酸味・塩味を控えめにする
- 辛味・苦味・渋味を積極的に取り入れると脂肪燃焼をサポート
- 6つの味をバランスよく摂ることで、消化力が高まり太りにくい体質に

食事の組み合わせの重要性
アーユルヴェーダでは、「食べ物の組み合わせ(サムヨガ)が消化に影響を与える」と考えます。
消化に負担のかかる組み合わせを避けることで、体に未消化物(アーマ)が溜まるのを防ぎ、脂肪がつきにくくなります!
避けるべき食べ合わせ
乳製品+酸味(ヨーグルト+フルーツ、チーズ+トマト)→消化が遅くなり、脂肪がつきやすい!
タンパク質+でんぷん(肉+ご飯、魚+パン)→ 消化に時間がかかり、腸内で発酵しやすい
冷たいもの+温かいもの(アイス+スープなど)→ 消化力が低下し、代謝が落ちる
果物+食事(フルーツ+食後のデザート)→ 果物は単体で食べるのがベスト!食後に食べると消化不良を起こしやすい
避けるべき食品&積極的に取り入れるべき食品
×避けるべき食品(脂肪がつきやすいもの)
- 冷たい飲み物・アイス → 消化力を低下させる
- 加工食品・揚げ物 → 消化が遅く、脂肪の蓄積につながる
- 白砂糖・人工甘味料 → 代謝を乱し、脂肪を増やす
- 小麦製品(パン・パスタ) → 消化に時間がかかり、脂肪になりやすい
- 食べ過ぎ・間食のしすぎ → 消化不良を起こし、代謝を低下させる
〇取り入れるべき食品(脂肪燃焼をサポートするもの)
- スパイス類(ターメリック、クミン、フェンネル、生姜)→ 代謝を上げ、脂肪燃焼を促進!
- 温かい飲み物(白湯、ハーブティー、スパイスティー)→ 消化力を高め、脂肪の蓄積を防ぐ
- 消化の良い炭水化物(キチュリ、雑穀、玄米)→ 体に優しく、エネルギー代謝を高る
- ギー(精製バター) → 消化をサポートし、脂肪をエネルギーとして活用しやすくする
- 苦味・渋味のある野菜(ゴーヤ、ケール、オクラ)→ 体内の余分な脂肪や毒素を排出
- 適度なタンパク質(ムング豆、ナッツ、豆腐)→ 消化に優しく、筋肉量を維持しながら脂肪を燃やす
まとめ
アーユルヴェーダ的ダイエットで脂肪燃焼!
- 6つの味をバランスよく摂ることで、消化力を整え脂肪燃焼を促す!
- 食べ合わせを意識することで、脂肪の蓄積を防ぐ!
- 避けるべき食品を控え、脂肪燃焼を助ける食品を取り入れる!
アーユルヴェーダでは、「太りやすいのは食事の量より、何をどう食べるか」がポイント!
少しずつ食習慣を見直して、お腹の脂肪を減らしていきましょう
お腹の脂肪を減らす!アーユルヴェーダ的アプローチ⑨
おなかの脂肪減少のための日々のルーチン
2025/03/23

「お腹の脂肪が気になる…」「運動や食事制限をしているのに、なかなか効果が出ない…」
そんなあなたにおすすめなのが、アーユルヴェーダ的なライフスタイルの見直し!
アーユルヴェーダでは、体のリズムに沿った生活をすることで、消化力(アグニ)を高め、脂肪燃焼を促進できると考えます。
今回は、朝・昼・夜のルーチンを整えて、無理なくお腹の脂肪を減らす方法をご紹介します!
朝のルーチンで代謝アップ!
アーユルヴェーダでは、「朝の過ごし方が1日を決める」と言われるほど、朝のルーチンは大切。
特に、カパの時間帯(6:00〜10:00)は体が重くなりやすく、脂肪が蓄積されやすい時間。
この時間にスッキリ目覚めて、体を活性化させることがポイントです!
おすすめの朝習慣

- 早起き(理想は6時前)
→ カパの影響を受ける前に起きることで、体が軽くスッキリ!
- 白湯を飲む(レモンや生姜を加えると◎)
→ 消化力を目覚めさせ、デトックスを促進!
- オイルうがい(ガンドゥーシャ)
→ ココナッツオイルやセサミオイルで口をすすぐと、毒素排出+代謝アップ!
- 朝の軽い運動(ヨガや散歩)
→ 体を動かすことで血流を促進し、脂肪燃焼をサポート!
- 消化に優しい朝食をとる
→ 果物、温かいスープ、ハーブティーなど、消化に負担のないものを選ぶ!

食事のリズムとタイミングが脂肪燃焼のカギ!
アーユルヴェーダでは、「食べる時間帯を意識することが、脂肪燃焼につながる」と考えます。
- ピッタの時間(10:00〜14:00)は消化力が最も高い!
- カパの時間(6:00〜10:00 / 18:00〜22:00)は消化が遅く、脂肪がつきやすい!
このリズムを意識して、食事のタイミングを調整することが大切です。
理想的な食事のスケジュール
- 朝食(7:00〜9:00)
→ 軽めにするのがベスト!白湯、スープ、フルーツなど。
- 昼食(12:00〜14:00)
→ 1日のメインの食事!消化力が最も高い時間なので、しっかり食べる。
→ スパイス(クミン、フェンネル、ターメリック)を活用すると◎
- 夕食(18:00〜20:00)
→ 軽め&早めに食べる!遅くなりすぎると脂肪になりやすい。
→ スープや温野菜、消化の良いタンパク質を中心に!

ポイント
- 夜遅くの食事はNG!
- 食事の間隔をしっかり空ける(理想は4〜6時間)
- 寝る2時間前までには食事を済ませる
夜の過ごし方で脂肪燃焼効果が変わる!
夜は、体がリラックスモードに入るヴァータ&カパの時間帯(18:00〜22:00)。
この時間の過ごし方が、翌日の消化力と脂肪燃焼に影響を与えます!
脂肪燃焼を高める夜習慣
- 軽めの夕食をとる(消化に負担をかけない)
→ スープ、蒸し野菜、キチュリ(ムング豆と米のお粥)などがおすすめ!
- 就寝前のアーユルヴェーダティーを飲む
→ 生姜・ターメリック・カルダモン入りのハーブティーで代謝アップ!

- 夜のリラックスタイムを大切にする
→ ストレスが多いと、コルチゾール(脂肪をためるホルモン)が増える!
→ ヨガ、アビヤンガ(セルフマッサージ)、瞑想などを取り入れると◎
- 22時〜23時には就寝する!
→ 夜更かしは脂肪燃焼を妨げる!成長ホルモンの分泌を活かすには早寝がカギ!
NG習慣
- スマホ・PCを寝る直前まで見る → 自律神経が乱れる
- 夜遅くの食事や間食 → 脂肪がつきやすくなる
- 夜更かし → 睡眠不足は脂肪燃焼の大敵!
まとめ:アーユルヴェーダのリズムで脂肪燃焼をサポート!
・朝のルーチンで消化力を高める!(白湯・軽い運動・オイルうがい)
・食事のリズムを意識して、脂肪が燃えやすいタイミングで食べる!
・夜の過ごし方で、翌日の代謝をアップ!(軽めの夕食・リラックス・早寝)
お腹の脂肪を減らすためには、毎日の生活リズムを整えることが大切!
今日からできることを、少しずつ取り入れてみてくださいね。
お腹の脂肪を減らす!アーユルヴェーダ的アプローチ⑧
おなかの脂肪減少のためのヨガポーズ
2025/03/22

「食事を気をつけているのに、お腹の脂肪がなかなか落ちない…」
そんな方におすすめなのが、**ヨガと呼吸法(プラーナーヤーマ)**を取り入れること
ヨガのポーズと呼吸を組み合わせることで、内臓を刺激し、代謝を上げ、脂肪燃焼をサポートします。
今回は、特にお腹周りの脂肪を落とすのに効果的なヨガポーズと呼吸法をご紹介します!
おなかの脂肪燃焼におすすめのヨガポーズ
- 舟のポーズ(ナヴァーサナ)

効果:腹筋を鍛え、消化力をアップ!
やり方
・床に座り、両膝を立てる。
・背筋を伸ばしたまま、両足を持ち上げる(膝を伸ばせる人は伸ばす)。
・両手を前に伸ばし、バランスをとる。
・深く呼吸しながら、30秒〜1分キープ。
ポイント:背中が丸まらないようにし、お腹の力でキープすること!
- ねじりのポーズ(アルダ・マッチェーンドラーサナ)

効果:内臓のデトックスを促し、ウエストを引き締める!
やり方
・床に座り、右足を左太ももの外側に置く。
・左肘を右膝にかけ、右手を後ろに置いて上体をねじる。
・深く呼吸しながら30秒キープし、反対側も同じように行う。
ポイント:息を吐くときにさらにねじると、内臓マッサージ効果アップ!
- 板のポーズ(プランク)

効果:体幹を強化し、お腹全体を引き締める!
やり方
・うつ伏せになり、腕を肩の下につく。
・足を後ろに伸ばし、つま先と腕で体を支える。
・背中をまっすぐにし、お腹を引き締めたまま30秒〜1分キープ。
ポイント:お尻が上がったり下がったりしないように、お腹の力を意識すること!
- 弓のポーズ(ダヌラーサナ)
効果:腹部の血流を良くし、消化を促進!
やり方
・うつ伏せになり、両足を曲げる。
・両手で足首をつかみ、息を吸いながら上体と足を持ち上げる。
・そのまま深呼吸しながら、30秒キープ。
ポイント:首に力を入れすぎず、胸を開くイメージで!
呼吸法(プラーナーヤーマ)と脂肪燃焼の関係
ヨガのポーズと一緒に行いたいのが、呼吸法(プラーナーヤーマ)。
正しい呼吸を行うことで、体のエネルギー循環を良くし、脂肪燃焼を促進します!
脂肪燃焼に効果的な呼吸法
- カパラバティ呼吸(火の呼吸)
効果:腹筋を鍛え、内臓のデトックスを促す!
やり方
・背筋を伸ばして座る。
・鼻から息を吸い、お腹をへこませながら勢いよく鼻から息を吐く。
・これを1秒に1回のペースで30回ほど繰り返す。
ポイント:お腹をしっかり動かし、腹筋を意識すること!
- 片鼻呼吸(ナーディ・ショーダナ)
効果:自律神経を整え、ストレスによる食べ過ぎを防ぐ!
やり方
・右手の親指で右鼻を押さえ、左鼻から息を吸う。
・右鼻を開き、左鼻を押さえて息を吐く。
・これを左右交互に行い、5分ほど続ける。
ポイント:ゆっくりと深く呼吸し、心を落ち着かせること!

まとめ:ヨガと呼吸でお腹スッキリ!
・ 舟のポーズ、ねじりのポーズ、プランク、弓のポーズでお腹の脂肪燃焼を促進!
・カパラバティ呼吸で脂肪燃焼力アップ、片鼻呼吸でストレスによる食べ過ぎを防ぐ!
・ヨガと呼吸を組み合わせることで、脂肪燃焼+内臓デトックス+ストレスケアができる!
お腹の脂肪を減らすには、食事・運動・呼吸のバランスが大切。
無理のない範囲で、毎日5分からでもヨガを取り入れてみましょう!
お腹の脂肪を減らす!アーユルヴェーダ的アプローチ⑦
おなかの脂肪減少のためのアーユルヴェーダ解毒(デトックス)
2025/03/21

「食事制限も運動も頑張っているのに、お腹の脂肪がなかなか落ちない…」
そんな方は、体に**毒素(アーマ)**が溜まっている可能性があります!
アーユルヴェーダでは、脂肪燃焼を促すために、まず**デトックス(解毒)**を行うことが大切。
今回は、アーユルヴェーダのデトックス法と、おうちで簡単にできる方法を紹介します!
アーユルヴェーダのデトックス「パンチャカルマ」とは?
アーユルヴェーダの最も強力な浄化療法が「パンチャカルマ」。
これは、体に溜まった毒素を排出し、消化力(アグニ)を回復させるための本格的なデトックス法です。
- パンチャカルマ 5つの浄化法
・ヴァマナ(嘔吐療法) → 体内の余分な粘液を排出
・ヴィレーチャナ(下剤療法) → 胃腸の浄化
・バスティ(浣腸療法) → 腸内の老廃物を取り除く
・ナスヤ(鼻浄化療法) → 鼻や頭部の浄化
・ラクタモクシャナ(瀉血療法) → 血液の浄化
このパンチャカルマ、本格的に受けるには専門施設での指導が必須なのですが…。
実は、**日本ではパンチャカルマを受けられる施設がほぼありません!
本場のパンチャカルマは、インドやスリランカのアーユルヴェーダ病院や専門リゾートで行われることが一般的。
期間は1〜4週間ほどで、個別の体質診断に基づいた徹底的なケアが受けられます。
「本格的に受けたいけど、海外に行くのは難しい…」
そんな方は、日本でも自宅でできる簡単なアーユルヴェーダ的デトックスを取り入れてみましょう!
- 自宅でできる簡単なアーユルヴェーダデトックス法
「本格的なデトックスはハードルが高い…」
そんな方でも、日常生活で無理なく取り入れられる方法をご紹介します!
①朝の白湯習慣で体をリセット
→ 毎朝1杯の白湯を飲むだけで、消化力(アグニ)を目覚めさせ、体内の毒素を洗い流します。
作り方:
水を沸騰させ、50℃くらいまで冷ます
ゆっくりと飲む(ゴクゴク飲まず、少しずつ)
生姜やレモンを加えると、さらにデトックス効果アップ!
② ギー断食(ギートックス)で脂肪燃焼
→ 朝食をギー(精製バター)に置き換える方法で、脂肪燃焼を促進!
やり方:
朝、スプーン1杯のギーを溶かした白湯を飲む
30分後に普通の食事を摂る(または軽めのフルーツ)
ギーは脂肪を燃やし、腸内の毒素を排出するのに役立ちます!
③デトックスハーブティーを飲む
→ 体質別に合ったハーブティーを飲むことで、余分な脂肪や老廃物を排出!
・ ヴァータ体質 → ジャタマンシー、アシュワガンダ(リラックス & 消化サポート)
・ ピッタ体質 → アロエベラ、コリアンダー(体の熱を鎮める)
・カパ体質 → 生姜、黒胡椒、ターメリック(脂肪燃焼促進)
飲み方:
1日2〜3杯、食前または食後に飲む
- デトックスにおすすめの食材
デトックスを効果的に進めるには、消化に良い食材を選ぶことが大切です。
積極的に摂るべき食材
・ 消化を助けるもの → 生姜、ターメリック、レモン
・ 腸をきれいにするもの → トリファラ(ハーブブレンド)、ギー
・ 脂肪燃焼を促すもの → 黒胡椒、シナモン、クミン
避けたほうがいい食材
・ 重たいもの → 揚げ物、乳製品(特にチーズやヨーグルト)
・ 冷たいもの → アイス、冷たい飲み物(消化力を弱める)
・ 砂糖 & 小麦製品 → 白砂糖、パン、パスタ(毒素を溜めやすい)
食事は「シンプル & 温かいもの」を意識するのがポイント!
まとめ:デトックスで脂肪を燃やしやすい体に!
✔ 日本でも白湯・ギートックス・ハーブティーなどの簡単デトックスで脂肪燃焼体質に!
✔ 食事を見直して、毒素を溜めない食生活を心がけよう!
デトックスを取り入れることで、体の巡りが良くなり、脂肪が燃えやすい体へと変わっていきます!
次回は 「アーユルヴェーダ的・脂肪燃焼のための運動法」 をご紹介します!お楽しみに。
お腹の脂肪を減らす!アーユルヴェーダ的アプローチ⑥
「おなかの脂肪減少に役立つアーユルヴェーダハーブ」
2025/03/20

「なかなか落ちないお腹の脂肪…どうにかしたい!」
そんな方におすすめなのが、アーユルヴェーダのハーブ です
アーユルヴェーダでは、
体質(ドーシャ)に合わせたハーブを取り入れることで、脂肪の燃焼をサポートし、健康的な体を目指します。
今回は、ヴァータ・ピッタ・カパの3つの体質別に、お腹の脂肪減少に役立つハーブ を紹介します!
ヴァータ体質:心と消化を整え、脂肪の蓄積を防ぐ
ヴァータ体質の人は、もともと痩せ型 で、エネルギー消費が激しい傾向がありますが、不規則な生活やストレスによって消化力(アグニ)が乱れると、脂肪がつきやすくなる ことがあります。
ヴァータ体質におすすめのハーブ
✅ カルダモン & コリアンダー → 消化を助け、胃腸の負担を軽減
✅ ブラーフミ & ジャタマンシー → ストレスを和らげ、心を落ち着かせる
✅ アシュワガンダ → ストレス太りを防ぎ、体力をサポート
✅ グッグル(Guggul) → 体を温め、デトックスを促す
・取り入れ方
✅ 食事にカルダモンやコリアンダーを加える(スープやお茶に◎)
✅寝る前にアシュワガンダミルクを飲む(小さじ1/2の粉末+ホットミルク)
✅グッグルはカプセルで1日2回摂取(1回250mg)
ピッタ体質:体の熱をコントロールし、脂肪を燃やす
ピッタ体質の人は、もともと代謝が活発で、脂肪がつきにくい ですが、食べすぎやストレスが原因で、お腹周りに脂肪がつくことがあります。
過剰な体の熱(アーマ)を鎮めながら、脂肪燃焼を促すハーブ を取り入れるのがポイント!
ピッタ体質におすすめのハーブ
✅ アロエベラジェル → 体内の熱を鎮め、消化を助ける
✅ カトゥカ → 肝臓をサポートし、脂肪代謝を促進
✅ ターメリック → 体内の炎症を抑え、脂肪の分解を助ける
・取り入れ方
✅朝、アロエベラジェルをスプーン1杯飲む(そのまま or 水と混ぜて)
✅ターメリックを料理に加える(カレーやスープ)
✅カツカはカプセルで摂取(1日2回、食後)
カパ体質:脂肪の燃焼を促し、むくみを防ぐ
カパ体質の人は、もともと脂肪や水分をためやすい ので、脂肪燃焼を助けるスパイスやハーブを積極的に取り入れる ことが重要です!
カパ体質におすすめのハーブ
✅ 黒胡椒 & 生姜 → 代謝を上げ、脂肪燃焼を促す
✅ ターメリック → 体を温め、脂肪分解を助ける
✅ トリカツ(黒胡椒・生姜・長胡椒のブレンド) → 消化力を高め、脂肪燃焼をサポート
✅ カツカ & トリファラ & ググル → 体脂肪の除去と水分の排出を助ける
・取り入れ方
✅ 朝、白湯に生姜パウダーや黒胡椒を入れて飲む
✅ トリカツパウダーを食事に加える(スープやおかゆに◎)
✅ ググルのカプセルを1日2回摂取(1回250mg)
まとめ:体質別のハーブを活用して、お腹の脂肪を落とそう!
✔ ヴァータ体質 → 消化を整え、ストレスケア(カルダモン、アシュワガンダ、ググル)
✔ ピッタ体質 → 体の熱をコントロール(アロエベラ、カトゥカ、ターメリック)
✔ カパ体質 → 脂肪燃焼を促す(黒胡椒、生姜、トリカツ、グッグル)
アーユルヴェーダのハーブをうまく取り入れれば、無理な食事制限や過度な運動をしなくても、お腹の脂肪を減らすことができます!
次回は 「アーユルヴェーダ的・脂肪燃焼のための食事法」 をご紹介します!お楽しみに💛
お腹の脂肪を減らす!アーユルヴェーダ的アプローチ⑤
「カパ体質のおなかの脂肪対策」
2025/03/19

「ダイエットしてもなかなか痩せない…」「特にお腹周りの脂肪が落ちにくい…」そんな悩みを持っている方は、カパ体質 かもしれません。
カパ体質の人は 水と土のエネルギー を持ち、安定感・落ち着き・包容力 が特徴。
でも、代謝がゆっくりで脂肪をため込みやすい ため、意識して動かないと太りやすくなります。
今回は、カパ体質の人が無理なくお腹の脂肪を減らす方法 を解説します!
カパ体質の特徴
カパ(Kapha)は 「水」と「土」 の性質を持ち、安定・冷静・持久力 のエネルギーを持っています。
・カパ体質の人の特徴
✅ 体がどっしりしていて、筋肉も脂肪もつきやすい
✅ 代謝がゆっくりで、一度太ると痩せにくい
✅ むくみやすく、水分をためこみやすい
✅ のんびりしていて、動くのがちょっと面倒
✅ 甘いものやこってりしたものが好き
カパ体質の人は、体に「水」と「土」の要素が多いため、冷え・むくみ・脂肪の蓄積 につながりやすいです。
特に、運動不足や過食が原因で、お腹まわりに脂肪がつきやすくなります。
カパ体質の人におすすめの食事・ハーブ・ライフスタイル
カパ体質の人は、「体を温めること」「代謝を上げること」 を意識するのがポイントです!
・ おすすめの食事
✅ スパイスを活用し、体を温める
✅ 軽めで消化に良い食事を心がける
✅ 甘味・油分の多いものを控えめにする
・おすすめの食材
✅生姜、にんにく、唐辛子(体を温めて脂肪燃焼をサポート)
✅大根、キャベツ、ブロッコリー(消化を促し、デトックス効果)
✅玄米、キヌア(消化によく、エネルギーになりやすい)
✅レンズ豆、ひよこ豆(植物性タンパク質で代謝アップ)
✅レモン、グレープフルーツ(脂肪燃焼をサポート)
❌控えたほうがいい食べ物
✅甘いもの(ケーキ、チョコレートなどは脂肪をためこみやすい)
✅こってりした料理(揚げ物・クリーム系の料理は消化が遅い)
✅冷たい食べ物・飲み物(アイスや冷たいジュースは代謝を下げる)
・おすすめのハーブ・スパイス
✅シナモン(血行を良くし、脂肪燃焼を促進)
✅ブラックペッパー(消化力を高め、脂肪分解をサポート)
✅トリカトゥ(生姜・長胡椒・黒胡椒のブレンド)
・おすすめのライフスタイル
✅ 朝は軽めの食事でスタート(消化に負担をかけない)
✅ 日中はできるだけ体を動かす(歩く・階段を使うなど意識する)
✅ シャワーではなく、お風呂に入って体を温める(冷え対策)
✅ 部屋を明るくし、アクティブな雰囲気を作る(カパの「重さ」を軽くする)
・カパの脂肪燃焼に効果的な方法
カパ体質の人は、とにかく「動くこと」 が大事!
放っておくと、どんどん脂肪をためこんでしまうので、積極的に体を動かして代謝を上げましょう。
・おすすめの運動
✅ 有酸素運動(ランニング・ダンス・ジャンプ系の運動)(脂肪燃焼効果が高い)
✅ ピラティスやダイナミックなヨガ(カパの「重さ」を軽くする)
✅ 朝のストレッチ(体を目覚めさせ、代謝をアップ)

❌ 控えたほうがいい運動
✅ゆったりした運動(リラックス系のヨガや散歩だけでは脂肪が燃えにくい)
✅長時間の座りっぱなし(デスクワークの人はこまめに立ち上がる習慣を)
ポイント:脂肪燃焼のカギは「リズム」と「継続」!
毎日少しずつでもいいので、必ず体を動かす時間をつくることが大切!
まとめ
カパ体質の人が無理なくお腹の脂肪を減らすには、「体を温める」「脂肪燃焼を促す食事」「積極的に動く」 の3つが大事!
✅ スパイスを活用し、体を温める(生姜・シナモン・ブラックペッパー)
✅ 甘いもの・脂っこいものを控える(脂肪の蓄積を防ぐ)
✅ 有酸素運動を習慣にする(ランニング・ダンス・アクティブヨガ)
✅ 毎日少しずつでも動く習慣をつける(ストレッチ・階段を使うなど)
「急にハードなダイエットをする」のではなく、「毎日のちょっとした習慣を変える」ことが、カパ体質の人にはぴったりの方法です。
「動けば変わる!」を合言葉に、お腹の脂肪とサヨナラしましょう!
次回は 「脂肪燃焼を高める食事のコツ」 についてお話しします!お楽しみに!
お腹の脂肪を減らす!アーユルヴェーダ的アプローチ④
「ピッタ体質のおなかの脂肪対策」
2025/03/18

「食べすぎていないのに、お腹周りの脂肪が気になる…」そんなあなたは、ピッタ体質かもしれません。
ピッタ体質の人は、消化力が強く、食べたものをしっかりエネルギーに変えられるタイプ。
でも、ストレスや食事の影響で 内臓脂肪がつきやすくなる ことがあります。
今回は、ピッタ体質の特徴と、お腹の脂肪を減らすための食事・ライフスタイルについてお話しします!
ピッタ体質の特徴
ピッタ(Pitta)は 「火」と「水」のエネルギー を持ち、 熱・鋭さ・変換力 が特徴です。
・ ピッタ体質の人の特徴
✅ もともと筋肉質で体力がある
✅ 代謝が活発で、食べるとすぐエネルギーになる
✅ お腹がすきやすく、食事を抜くとイライラしがち
✅ 暑がりで、汗をかきやすい
✅ 皮膚が赤くなりやすく、ニキビや炎症が出やすい
ピッタ体質の人はエネルギーの消費が早いですが、 食事のとり方を間違えると、脂肪をため込みやすくなります。
特に、過剰な食欲やストレス が内臓脂肪の原因になりやすいので、体の「火」をコントロールすることが大切です。
・ピッタ体質の人におすすめの食事・ハーブ・ライフスタイル
ピッタ体質の人は、 「火」を鎮める食事と生活習慣 を意識しましょう。
・おすすめの食事
✅ 冷やしすぎず、適度に体をクールダウンする食材
✅ 甘味・苦味・渋味のある食べ物をとる(緑黄色野菜・果物・豆類)
✅ 適度な油(ギー・ココナッツオイル)で胃腸を守る
✅ スパイスを控えめにし、穏やかな味つけを心がける
・おすすめの食材
✅きゅうり、ズッキーニ(体を冷やしすぎない適度なクールダウン)
✅セロリ、葉野菜(火のエネルギーを鎮める)
✅ギー、ココナッツオイル(消化を助け、内臓を守る)
✅白米、全粒穀物(胃腸に優しく、エネルギーを安定させる)
✅甘い果物(マンゴー、梨、ぶどうなど)
❌ 控えたほうがいい食べ物
✅辛いもの(唐辛子、にんにく、玉ねぎは熱を強める)
✅揚げ物・脂っこい食事(胃腸に負担をかけ、脂肪をため込みやすい)
✅アルコール・カフェイン(ピッタを刺激し、食欲を暴走させる)

・おすすめのハーブ・スパイス
✅コリアンダー(体の熱を和らげる)
✅フェンネル(消化を整えて脂肪の吸収を抑える)
✅アムラ(アマラキ)(体をクールダウンしながら栄養補給)
・おすすめのライフスタイル
✅ 食事は規則正しく、ゆっくり食べる(早食いは消化を乱す)
✅ 適度にリラックスする時間をとる(ストレスを減らす)
✅ 暑さを避け、涼しい環境で過ごす(熱をためすぎない)
✅ マッサージやアロマで心を落ち着ける(ピッタの炎を鎮める)
・ピッタの脂肪燃焼に効果的な方法
ピッタ体質の人は 筋肉量があり、運動するとすぐにエネルギーを消費できる ので、 無理のないペースで適度に運動する ことが大切です。
おすすめの運動
✅ ウォーキングや水泳(リラックスしながら脂肪を燃焼)
✅ ヨガ(特にクールダウン系のポーズ)(心身のバランスをとる)
✅ 適度な筋トレ(過度にハードな運動はストレスになるので注意)
❌ 控えたほうがいい運動
・高温での激しい運動(ホットヨガや炎天下でのランニングはNG)
・競争心をあおるスポーツ(ピッタの攻撃性を高め、ストレスに)
ポイント:脂肪燃焼には「クールダウン」が重要!
ピッタ体質の人は、ストレスや過度な刺激でお腹周りに脂肪をためこみやすいので、 「冷静さ」と「リラックス」を意識する ことが脂肪燃焼のカギになります。
まとめ
ピッタ体質の人が無理なくお腹の脂肪を減らすには、 「火のエネルギーを整える」「ストレスを減らす」「適度な運動」 の3つが大切!
✅ 甘味・苦味・渋味のある食材をとる(ピッタの炎を鎮める)
✅ アルコール・辛いもの・脂っこい食事は控える(脂肪の蓄積を防ぐ)
✅ ウォーキングや穏やかなヨガで脂肪燃焼を促す(過度な運動は逆効果)
✅ ストレスを減らす習慣をつくる(リラックスが脂肪燃焼のカギ)
「ストイックに頑張る!」ではなく、「心地よく続けられること」を意識して、お腹の脂肪を無理なく落としていきましょう♪
お腹の脂肪を減らす!アーユルヴェーダ的アプローチ③
「ヴァータ体質のおなかの脂肪対策」
2025/03/17

「もともと痩せやすいはずなのに、お腹の脂肪だけが気になる…」そんな悩みを持つ人は、ヴァータ体質の可能性があります。
ヴァータ体質の人は、エネルギーを消費しやすい一方で、代謝が乱れると脂肪がつきやすくなることも。
今回は、ヴァータ体質の特徴と、お腹の脂肪を減らすための食事・ライフスタイルについてお伝えします!
ヴァータ体質の特徴
ヴァータ(Vata)は 「風」と「空」のエネルギー を持ち、軽さや動きの多さが特徴です。
・ヴァータ体質の人の特徴
✅ 体が細く、筋肉がつきにくい
✅ 代謝が活発で、食べても太りにくい
✅ 乾燥しやすく、冷えやすい
✅ 活発だが、ストレスや疲れを感じやすい
✅ 食欲にムラがあり、食事の時間が不規則になりがち
一見、太りにくいタイプに思えますが、不規則な生活やストレスで消化力(アグニ)が弱まると、体がエネルギーをため込もうとして脂肪を蓄積することがあります。
特に、お腹周りに脂肪がつきやすくなるので、 「消化を整えること」と「体を温めること」 が大切です。
ヴァータ体質の人におすすめの「食事・ハーブ・ライフスタイル」
ヴァータ体質の人は、体を冷やさないよう 温かく、消化に優しい食事 を意識しましょう。
・おすすめの食事
✅ 温かいスープや煮込み料理(消化を助ける)
✅ ギー(精製バター)やオリーブオイル(体を潤す)
✅ 甘みのある食材(かぼちゃ、サツマイモ、ナッツ類)(エネルギーを補給)
✅ 炭水化物や適度なタンパク質をしっかりとる(代謝の安定)
・控えたほうがいい食べ物
✅生野菜や冷たい飲み物(体を冷やして消化を弱める)
✅コーヒーや刺激物(神経を興奮させて消化を乱す)
✅ファストフードや加工食品(消化不良の原因になる)
・おすすめのハーブ・スパイス
✅ショウガ(消化を助け、体を温める)
✅クミン(胃腸を整え、ガスを防ぐ)
✅アシュワガンダ(ストレスを和らげ、エネルギーを補う)
・おすすめのライフスタイル
✅ 朝は白湯を飲む(消化を目覚めさせる)
✅ 規則正しい食事を心がける(アグニを安定させる)
✅ オイルマッサージ(アビヤンガ)を取り入れる(乾燥を防ぎ、血流を良くする)
✅ 夜は早めに寝る(ヴァータの乱れを防ぐ)
・ヴァータの脂肪燃焼に効果的な方法
ヴァータ体質の人は、激しい運動よりも、 穏やかで継続しやすい運動 が効果的です。
☆おすすめの運動☆
・ヨガやストレッチ(体をほぐし、代謝を整える)
・ウォーキング(リズムを整えて脂肪燃焼を促す)
・加圧トレーニング(体温を上げ、代謝を安定させる)
❌ 過度なランニングやハードな筋トレは、ヴァータの乱れを引き起こしやすいので注意しましょう。
ポイント:脂肪燃焼のカギは「リラックス」!
ヴァータ体質の人は、ストレスや不安で体がエネルギーをため込みやすくなるので、 深呼吸や瞑想を取り入れてリラックスする ことも大切です。
まとめ
ヴァータ体質の人が無理なくお腹の脂肪を減らすには、 「消化力を整える」「体を温める」「リラックスする」 の3つが大切!
✅ 温かく消化に優しい食事をとる
✅ 白湯やスパイスでアグニを整える
✅ リズムのある運動やオイルマッサージを習慣にする
無理な食事制限やハードな運動ではなく、自分の体質に合った方法で、心地よく健康的に脂肪を落としていきましょう♪
お腹の脂肪を減らす!アーユルヴェーダ的アプローチ②
「アーユルヴェーダによるおなかの脂肪減少の考え方」
2025/03/16

お腹の脂肪が気になる人は多いですよね。
でも、ただ食事制限をしたり、運動をしたりするだけでは、なかなか落ちないこともあります。
アーユルヴェーダでは、お腹に脂肪がつく原因を「体のバランスの乱れ」と考え、それを整えることで無理なく健康的に脂肪を減らしていくことを目指します。
今回は、アーユルヴェーダ的に「なぜお腹に脂肪がつくのか?」を知り、それを改善するための基本的な考え方をお伝えします。
脂肪がたまりすぎる状態=メドーロガとは?
アーユルヴェーダでは、脂肪が過剰にたまる状態を 「メドーロガ」 と言われています。
脂肪は体を守るために必要なものですが、増えすぎると代謝が落ち、体が重くなり、疲れやすくなってしまいます。
特に、お腹に脂肪がたまりやすいのは、体の中の 「消化の火(アグニ)」 が弱くなっているからだと考えられています。
食べたものをしっかりエネルギーに変える力が低下すると、余った栄養が脂肪として蓄積されてしまうのです。
体質(ドーシャ)とお腹の脂肪の関係
アーユルヴェーダでは、人それぞれ 「ドーシャ(体質)」 があり、それによって脂肪のつきやすさが変わると考えられています。
・ヴァータ(風の性質が強いタイプ)
もともと痩せやすい体質ですが、不規則な生活やストレスが続くと、代謝が乱れ、お腹周りに脂肪がつくことがあります。
・ピッタ(火の性質が強いタイプ)
代謝が活発で脂肪がつきにくい傾向がありますが、食べ過ぎやストレスが原因で脂肪が増えることもあります。
・カパ(水の性質が強いタイプ)
もともと脂肪をためやすい体質で、特にお腹や腰周りに脂肪がつきやすい傾向があります。
食べすぎや運動不足によって太りやすくなります。
特に カパタイプ の人は、脂肪がたまりやすいので、普段から 消化力(アグニ)を高めること や 体を動かすこと を意識することが大切です。
消化の火(アグニ)を強くして脂肪を燃やす!
アーユルヴェーダでは、食べたものをエネルギーに変える「消化の火(アグニ)」の働きがとても重要だと考えます。
アグニが弱まると、消化しきれなかった食べ物が 「アーマ(未消化物)」 となり、それが脂肪として体にたまりやすくなってしまいます。
アグニを強くするために大切なこと!!
✅ 温かい飲み物をとる → 白湯を飲むことで消化力を高め、脂肪の燃焼を助けます。
✅ スパイスを取り入れる → ショウガやターメリック、ブラックペッパーなどのスパイスは、消化を助けて脂肪を燃やしやすくします。
✅ 夜遅くに食べすぎない → 夜遅くの食事は消化力が落ち、脂肪として蓄積されやすくなります。
✅ 食べ過ぎを避ける → 満腹になるまで食べるのではなく、「少し余裕がある」と感じるくらいでやめることが大切です。
アグニを活性化させることで、体内の代謝が上がり、お腹の脂肪がたまりにくくなります。
お腹に脂肪がつくのは、単なる食べすぎや運動不足だけが原因ではありません。
アーユルヴェーダでは、 消化力(アグニ)の低下 や 体質(ドーシャ)の乱れ も脂肪増加の原因になると考えます。
ポイントは
✅ 自分の体質(ドーシャ)を知ること
✅ 消化の火(アグニ)を強くすること
この2つを意識することで、無理なく健康的に脂肪を減らすことができます。
次回は 「ヴァータ体質のおなかの脂肪対策」 についてお話しします!お楽しみに✨
お腹の脂肪を減らす!アーユルヴェーダ的アプローチ①
「お腹の脂肪はなぜ落ちにくいのか?」
2025/03/15

お腹の脂肪はなぜ落ちにくいのか?
お腹まわりの脂肪、気になりますよね。
ダイエットをしてもなかなか落ちにくい部分として、多くの人が悩んでいます。
しかし、お腹の脂肪は単なる見た目の問題ではなく、健康リスクとも深く関係しています。
アーユルヴェーダの視点から見ると、脂肪の蓄積は「メーダ・ダートゥ」(脂肪組織)のバランスの乱れによって起こります。
特に、お腹周りに脂肪がつきやすい人は、体質やライフスタイルに何らかの偏りがある可能性があります。
1. お腹の脂肪が落ちにくい理由
お腹に脂肪がつきやすい原因はいくつか考えられます。
●ホルモンバランスの影響
ストレスが多いと、コルチゾール(ストレスホルモン)が過剰に分泌され、内臓脂肪が増えやすくなります。
●消化力の低下
アーユルヴェーダでは「アグニ(消化の火)」が弱ると、代謝が落ち、未消化物(アーマ)が体内に蓄積されると考えられています。
これが脂肪として蓄積される原因になります。
●食生活の偏り
過剰な糖質や加工食品の摂取は、体脂肪の増加を促します。
特にヴァータ体質の人は不規則な食事で消化力が乱れ、カパ体質の人は甘いものや油分を多く摂りすぎる傾向があります。
アーユルヴェーダでは、適度な運動が「アグニ」を活性化し、脂肪燃焼を促進すると考えられています。
カパ体質の人は特に運動不足による脂肪の蓄積が起こりやすいです。
これらの原因を見ると、更年期世代が太りやすいのも納得ですね…。
実際に、サロンのお客様からはこんな切実なお声が届いています。
「全部あてはまるわー!! 更年期になると嫌でもホルモンバランスが乱れるし、年齢とともに消化力の低下も実感…。
食事を作るのが億劫で、つい外食やお惣菜に頼りがち。運動しなきゃと思いつつ、時間がないを言い訳にしてる自分がいる(笑)」
次回は「アーユルヴェーダによるおなかの脂肪減少の考え方」についてご紹介します。
お楽しみに!
お腹の脂肪を減らす!アーユルヴェーダ的アプローチ
2025/03/14
お腹がぽっこり出ていると、なんだか気になりますよね。
お気に入りの服を着たくても、お腹が目立つからやめたこと、ありませんか?
アーユルヴェーダのケアで、スッキリボディへ!
現代には数え切れないほどのダイエット方法や減量サプリがありますが、それらの中には効果が乏しいものも少なくありません。
アーユルヴェーダでは、無理のない自然な方法で健康的に体重を減らすことを推奨しています。
あなたの体質に合ったアプローチを見つけて、無理なく理想の体型へと近づけていきましょう。
次回は「お腹の脂肪はなぜ落ちにくいのか?」をお伝えします。
アーユルヴェーダ式・水の飲み方完全ガイド 〜体質に合った水習慣で健康を手に入れる〜⑧
2025/03/13
水と心のつながり
実は、水は体だけでなく、心のバランスを整えるのにも役立ちます。
アーユルヴェーダでは、水には落ち着きや安心感を与えるエネルギーがあるとされています。
🌙 心を落ち着ける水の飲み方
・ゆっくりと、一口ずつ味わって飲む
・ストレスを感じたら白湯を飲んでリラックス
・寝る前に温かい水を飲むと、安眠効果も◎
日々の生活の中で、水を意識するだけで、心身のバランスが整っていきますよ!
8回にわたって、水の力とアーユルヴェーダの知恵についてお届けしてきましたが、いかがでしたか?
水は私たちの体を潤すだけでなく、心のバランスを整え、生命エネルギーを高める大切な存在です。
「いつ、どのように飲むか」
を少し意識するだけで、体調や気分が驚くほど変わってくるはずです。
まずはできることから、無理なく取り入れてみてください。
朝の白湯を習慣にする、食事の30分前に水を飲む、ストレスを感じたら一口の温かい水で気持ちを落ち着ける。
そんな小さな積み重ねが、心身の健康へとつながります。
自分に最適な水の飲み方を見つけ、健やかで心地よい毎日を過ごしてくださいね!
アーユルヴェーダ式・水の飲み方完全ガイド 〜体質に合った水習慣で健康を手に入れる〜⑦
2025/03/12
水とデトックスの関係
アーユルヴェーダでは、水は体の老廃物を流し、デトックスを助ける大切な役割を果たします。
特に次のようなポイントを意識すると、スムーズに毒素を排出できます。
💧 朝の白湯でリセット
→ 眠っている間にたまった毒素を流し、消化器官を整えます。
🚶♀️ 軽い運動+水
→ 汗をかくことで、老廃物を排出しやすくなります。
🥦 食事と一緒に適量の水を
→ 食事中に少量の水を飲むことで、消化がスムーズになります。
しっかり水を飲んで、体の内側からキレイを目指しましょう!
次回は最終回、「水と心のつながり」についてお話しします。
アーユルヴェーダ式・水の飲み方完全ガイド 〜体質に合った水習慣で健康を手に入れる〜⑥
2025/03/11
水分不足のサインに気づこう!
実は、のどが渇いたと感じた時点で、すでに体は軽い脱水状態になっています。
こんなサインが出ていたら、水が足りていないかも!?
🚨 水分不足のサイン
✅ 口が渇く、唇がカサカサする
✅ 便秘がちになる
✅ 肌が乾燥する
✅ 頭痛やめまいが起こる
✅ 疲れやすくなる
こまめに水を飲むことで、体内の巡りがよくなり、疲れにくくなりますよ!
次回は「水とデトックスの関係」についてご紹介します。

アーユルヴェーダ式・水の飲み方完全ガイド 〜体質に合った水習慣で健康を手に入れる〜⑤
2025/03/10
水の温度と消化の関係
「冷たい水のほうがスッキリするから好き!」という方もいるかもしれません。
でも、アーユルヴェーダでは水の温度が消化力に大きく影響すると考えられています。
🌡 冷たい水(消化を弱める)
・消化力を低下させ、食べたものの吸収を妨げる
・脂肪の代謝を悪くし、体が冷えやすくなる
🔥 温かい水(白湯)(消化を助ける)
・胃腸を温め、消化力を高める
・血流を促し、デトックスをサポート
特に食事中や食後すぐに冷たい水を飲むと、消化が遅くなり、体に負担がかかることも。
できるだけ常温または温かい水を飲むようにしてみてくださいね!
次回は「水分不足のサイン」についてお話しします。
アーユルヴェーダ式・水の飲み方完全ガイド 〜体質に合った水習慣で健康を手に入れる〜④
2025/03/09
水を飲むベストなタイミング
「水を飲むタイミング」を意識すると、体の調子がさらに整います。
アーユルヴェーダでは、特に次のタイミングをおすすめしています。
✅ 朝起きてすぐ(白湯がベスト!)
→ 消化器官を目覚めさせ、デトックスを促します。
✅ 食事の30分前
→ 胃腸を準備し、消化を助けます。
✅ 食後1時間後
→ 栄養の吸収を高め、体に負担をかけません。
✅ 運動後
→ 汗で失われた水分を補給し、筋肉をサポート。
これらのタイミングを意識すると、ただ水を飲むだけでなく、体の調子を整える手助けになりますよ。
次回は「水の温度と消化の関係」についてご紹介します!
アーユルヴェーダ式・水の飲み方完全ガイド 〜体質に合った水習慣で健康を手に入れる〜①
2025/03/06
水と私たちのカラダの関係
こんにちは!
みなさんは普段、水をどれくらい意識して飲んでいますか?
「1日2リットルがいいって聞いたことがある」「のどが渇いたら飲むようにしている」など、水の飲み方は人それぞれですよね。
でも、実は水の飲み方ひとつで体の調子が変わるって知っていましたか?
アーユルヴェーダでは、水はただの「水分補給」ではなく、体のエネルギーを整える大切な役割を持っていると考えられています。
正しく飲めば、消化がよくなったり、むくみが取れたり、疲れにくくなったりと良いことばかり。
でも、間違った飲み方をしてしまうと、逆に体の不調につながることもあるんです。
これから8回に分けて、アーユルヴェーダ的な「水の飲み方」について詳しくお伝えしていきます。
今日のテーマは、水と私たちのカラダの関係について!
水は生命の源!カラダの60%は水
「水がなければ生きていけない」と言われるように、私たちのカラダの約60%は水でできています。
血液、リンパ液、消化液…すべてが水をベースにして働いています。
水の主な役割は、
✅ 栄養を運ぶ
✅ 老廃物を排出する
✅ 体温を調整する
✅ 関節や筋肉の動きをスムーズにするなど、たくさんあります。

でも、ただ水を飲めばいいわけではなく、「どのタイミングで、どの温度の水を、どのくらい飲むか」がとても大切なんです。
アーユルヴェーダが大切にする「水の性質」
アーユルヴェーダでは、水は「冷却」と「滋養」のエネルギーを持っていると考えられています。
特に、
✔️ 心を落ち着かせる
✔️ 胃腸を潤す
✔️ 体のバランスを整える
といった効果があります。
一方で、「飲み方」によっては消化の力を弱めたり、体内の老廃物をため込んでしまう原因になることも。
そこで、次回はアーユルヴェーダが考える「水の力」について、もう少し詳しくご紹介します!
普段、何気なく飲んでいる水ですが、意識して飲むだけで体の変化を感じられるかもしれませんよ♪
アーユルヴェーダ式・水の飲み方完全ガイド 〜体質に合った水習慣で健康を手に入れる〜③
2025/03/06
体質別・正しい水の飲み方
アーユルヴェーダでは、ヴァータ・ピッタ・カパという3つのドーシャ(体質)によって適した水の飲み方が異なります。
🌿 ヴァータ体質(風のエネルギーが強い人)
・温かい水をこまめに飲む
・白湯を朝一番に飲むと良い
・冷たい水は避ける
🔥 ピッタ体質(火のエネルギーが強い人)
・常温または少し冷ました水を飲む
・食事中に少量ずつ飲むのが◎
・氷水の飲みすぎには注意
🌱 カパ体質(水のエネルギーが強い人)
・温かい水を適量飲む
・日中は少しずつ飲むと良い
・朝一番の白湯が代謝を高める
あなたの体質に合った飲み方を意識してみてくださいね!
次回は、「水を飲むベストなタイミング」についてお話しします。
アーユルヴェーダ式・水の飲み方完全ガイド 〜体質に合った水習慣で健康を手に入れる〜②
2025/03/06
アーユルヴェーダが考える『水』の力
アーユルヴェーダでは、水は「ソーマ(Soma)」と呼ばれ、月のエネルギーを持つとされています。
このエネルギーには、冷却作用や滋養作用があり、私たちの体を健やかに保つ働きがあるのです。
また、水には次のような特性があると考えられています。
✅ 浄化(Mrushta): 体を清潔に保つ
✅ 活力を与える(Jeevana): 体を元気にする
✅ 満たす(Tarpana): 心身を潤し、満足感を与える
✅ 心を健やかにする(Hrudya): 精神の安定を促す
こうした水の特性を最大限に活かすためには、正しい飲み方をすることが大切です。
次回は「あなたの体質別・正しい水の飲み方」をご紹介します!
第5回:アーユルヴェーダ ~五大元素のバランスの大切さ~
地の役割
2025/03/05

パンチャ・マハーブータ(五大元素)
地の役割
●地(プリトヴィ / Earth)
地は、「安定性」と「構造」を司る要素です。
骨や筋肉、皮膚、歯などの身体の構成要素を支えます。
心の面では、地の要素が強いと忍耐力があり、落ち着いた性格になりますが、過剰になると頑固さや執着心につながることもあります。
五大元素のバランスが大切
五大元素は、それぞれが絶妙なバランスを保つことで、私たちの健康や精神状態を維持しています。
しかし、生活習慣や環境の影響でバランスが崩れると、不調や病気の原因になります。
アーユルヴェーダでは、自分の体質(ドーシャ)を理解し、五大元素のバランスを整えることが大切です。
例えば、火の要素が強い人は冷たい食べ物を摂ることでバランスを取ることができます。
まとめ
五大元素は、私たちの身体と心に深く関わる大切なエネルギーです。
アーユルヴェーダの知恵を日常に取り入れることで、より健康でバランスの取れた生活を送ることができます。
ぜひ、自分の体質や五大元素のバランスを意識しながら、日々の生活に役立ててみてください!
第4回:アーユルヴェーダ ~変化と潤いのエネルギー~
火と水の役割
2025/03/04

パンチャ・マハーブータ(五大元素)
火と水の役割
●火(テージャ / Fire)
火は、「変換」と「熱」のエネルギーです。消化や代謝、ホルモンの働きなどに関与し、視覚や知性にも影響を与えます。
火の要素が強いと、頭の回転が速く、リーダーシップを発揮しやすくなりますが、過剰になると怒りや攻撃性が増すこともあります。
●水(アップ / Water)
水は、「潤い」と「結束」をもたらす要素です。体内では血液やリンパ液、粘膜などを構成し、保湿や体温調整の役割を果たします。
精神面では、愛情や共感力に関係し、バランスが崩れると依存心が強くなったり、感情の起伏が激しくなることもあります。
次回は、「地」の役割と五大元素のバランスの大切さについてお話しします。
第3回:アーユルヴェーダ ~スペースと動きのエネルギー~
空と風の役割
2025/03/03

パンチャ・マハーブータ(五大元素)
空と風の役割
●空(アーカーシャ / Ether)
空は、すべてのものが存在するための「スペース」です。
私たちの身体の中では、内臓の空洞、血管、細胞の隙間などに空のエネルギーが関係しています。
精神面では、空の要素が高まると創造力や直感が冴え、逆にバランスを崩すと孤独感や空虚感を感じることがあります。
●風(ヴァーユ / Air)
風は、「動き」を司る要素です。呼吸や血液循環、筋肉の動き、神経伝達など、すべての運動に関与しています。
心の面では、風の要素が強いと活発でエネルギッシュになりますが、過剰になると不安やストレスを感じやすくなります。
次回は、「火と水」の役割についてお話しします。
第2回: アーユルヴェーダ ~すべてを構成する5つのエネルギー~
五大元素
2025/03/02

五大元素とは?
アーユルヴェーダでは、宇宙に存在するすべてのものは「空・風・火・水・地」の五大元素から成り立っていると考えます。
- 空(アーカーシャ / Ether) – 空間、広がり
- 風(ヴァーユ / Air) – 動き、変化
- 火(テージャ / Fire) – 変換、熱
- 水(アップ/ Water) – 流動性、結束
- 地(プリトヴィ / Earth) – 安定性、構造
これらの五大元素が組み合わさることで、私たちの身体、心、環境、さらには宇宙全体が成り立っています。
これらは私たちの体や心にも影響を与えます。
- 日常生活での活かし方
・体調や気分に合わせて、五大元素のバランスを意識した食事をとる
・日々の行動や環境を見直し、どの要素が不足・過剰かを考える
- 自分の体にこの要素が強く出ているかも?
・ある特定の気質が強く表れる(例:落ち着きがない、熱しやすい)
・特定の食べ物や天候によって体調が変わりやすい
次回からは、それぞれの元素の特徴と、身体や心にどのような影響を与えるのかを詳しく見ていきましょう。
-
 休んでいるのに疲れが抜けない理由
休んでいるのに疲れが抜けない理由― 回復できない体の仕組み ―「しっかり休んでいるはずなのに疲れが取れない」こ
休んでいるのに疲れが抜けない理由
休んでいるのに疲れが抜けない理由― 回復できない体の仕組み ―「しっかり休んでいるはずなのに疲れが取れない」こ
-
 健康は数値だけでは測れない
― 心・体・魂の調和というアーユルヴェーダの健康観 ―病院の検査で「異常はありません」と言われたにもかかわらず
健康は数値だけでは測れない
― 心・体・魂の調和というアーユルヴェーダの健康観 ―病院の検査で「異常はありません」と言われたにもかかわらず
-
 花粉症は「体内環境の乱れ」から始まる 1
花粉症は「体内環境の乱れ」から始まる花粉症は一般的に「免疫の過剰反応」と説明されますが、Ayurvedaではさ
花粉症は「体内環境の乱れ」から始まる 1
花粉症は「体内環境の乱れ」から始まる花粉症は一般的に「免疫の過剰反応」と説明されますが、Ayurvedaではさ
-
 「これだけ健康にも美容にも気を配ってきたのに、なぜ疲れが抜けないのか」
「これだけ健康にも美容にも気を配ってきたのに、なぜ疲れが抜けないのか」50代の女性から、非常に多くいただくご相
「これだけ健康にも美容にも気を配ってきたのに、なぜ疲れが抜けないのか」
「これだけ健康にも美容にも気を配ってきたのに、なぜ疲れが抜けないのか」50代の女性から、非常に多くいただくご相
-
 「アーユルヴェーダとは何か ― 心・体・魂を本来の調和へ戻すインドの伝統医学」
「アーユルヴェーダとは何か ― 心・体・魂を本来の調和へ戻すインドの伝統医学」最近、「しっかり寝ているのに疲れ
「アーユルヴェーダとは何か ― 心・体・魂を本来の調和へ戻すインドの伝統医学」
「アーユルヴェーダとは何か ― 心・体・魂を本来の調和へ戻すインドの伝統医学」最近、「しっかり寝ているのに疲れ
いつも当サロンをご利用いただき、誠にありがとうございます。
本日より、2月分の予約受付を開始いたしましたのでお知らせいたします。
2月は日数が短いため、例年週末を中心に予約が埋まりやすくなっております。
ご希望の日時がある方は、お早めのご予約をおすすめいたします。
平川ふゆ
新年あけましておめでとうございます!
旧年中は サロンドラヴィナをご愛顧いただき、誠にありがとうございました。
たくさんのお客様の笑顔に支えられ、素晴らしい一年を過ごすことができました。
2026年も、皆様にとって心からリラックスできる「癒やしの場所」であり続けられるよう、心を込めてお手入れさせていただきます。
また皆様にお会いできるのを楽しみにしております!
平川ふゆ
「年末年始はどうせ休みでしょ?」
そう思っている方へ。
当店は年末年始も通常営業です。
正月太りをつくらない。
生活リズムを崩さない。
いつも通り、淡々と身体を整える。
【1月の営業スケジュール】
1月1日
▶ 加圧トレーニングのみ対応
1月2日〜4日
▶ 通常営業(年末年始も通常通り)
1月10日〜11日
▶ 研修のため休業
1月19日〜26日
▶ 休業
1月は変則営業があります。
来店前に必ずカレンダーをご確認ください。
✨12月のお休みのお知らせ✨
いつもご利用いただきありがとうございます。
📅【休業日】
・毎週 月曜日・木曜日
・24日土曜日、25日日曜日は研修のためお休みをいただきます。
🕊ご予約について
・一般予約を開始いたしました。
・オンラインカウンセリング(マインドケアセラピー) は夜18時以降も受付中です。
・初めての方は 30分無料オリエンテーション をぜひお気軽にご利用ください。
皆さまにお会いできることを楽しみにしております💐
🌿1日2名様限定・完全予約制
ご希望日時がある場合は、お早めのご連絡をおすすめいたします。
空き状況は下記をクリック カレンダーをご確認ください。